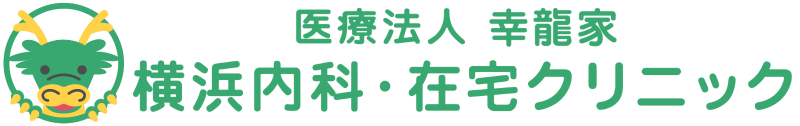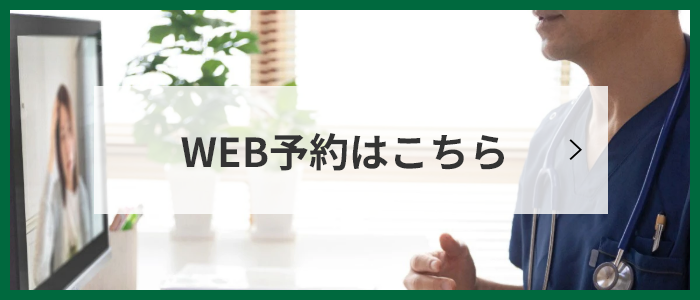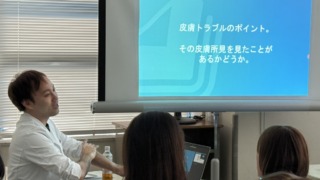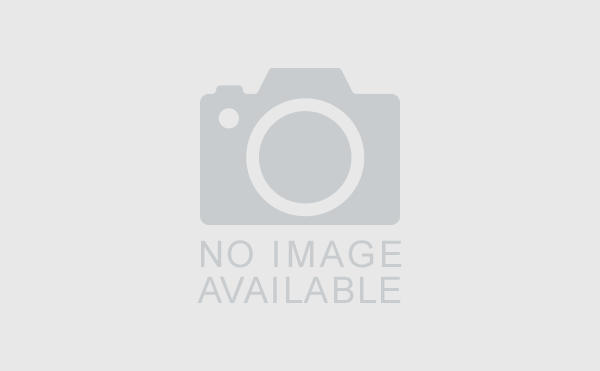インフルエンザの予防は必要?日常でできる予防方法とおすすめの食品を解説

インフルエンザが流行する季節が近づいてきましたね。
インフルエンザは、重症化のリスクがある方が感染すると命の危険もある感染症です。
今回は、日常生活でできる感染予防方法や、感染予防に有効な食品について紹介します。
インフルエンザ以外の感染症にも効果があるので、ぜひ参考にしてください!
- 1. インフルエンザの予防が必要な理由
- 2. インフルエンザの予防はワクチン接種から
- 2.1. ワクチン概要
- 2.2. ワクチンの効果
- 2.2.1. 【研究で実証された予防効果】
- 2.2.1.1. 高齢者(65歳以上)への効果
- 2.2.1.2. 小児への効果
- 3. 日常でできるインフルエンザ予防方法
- 3.1. 人混みに出ない
- 3.2. 手洗い・うがい
- 3.3. マスク着用
- 3.4. 部屋の温度・湿度管理
- 3.5. 十分な栄養補給と適度な運動
- 3.6. 薄着の習慣
- 4. インフルエンザに予防におすすめ食べ物
- 4.1. たんぱく質
- 4.1.1. 【おすすめの食品と特徴】
- 4.1.2. 【摂取のポイント】
- 4.2. ビタミンC
- 4.3. ビタミンA
- 4.4. 発酵食品
- 4.5. 食物繊維
- 4.6. 温かい食べ物
- 5. インフルエンザかも?病院受診のタイミング
- 6. 横浜内科・在宅クリニックでできる対応
- 7. まとめ
インフルエンザの予防が必要な理由

インフルエンザに感染した多くの方は軽症で回復します。
しかし、中には脳症や肺炎などの重篤な合併症を引き起こし、重症化してしまう可能性がある方もいます。
下記に当てはまる方は重症化リスクがあるため注意が必要です。
- 高齢者(65歳以上)
- 幼児(5歳未満)
- 妊婦
- 次の持病がある方
喘息
慢性呼吸器疾患(COPD)
慢性心疾患
糖尿病や高血圧などの代謝性疾患
腎機能障害
免疫機能不全
稀に健康な方でも重症化する可能性があります。
インフルエンザは、無症状や軽症の場合でも、周囲の方々への感染源となるので注意が必要です。
一人ひとりの予防対策が、自分自身はもちろん、大切な家族や周囲の方々の命を守ることにつながります。
社会全体で感染症対策に取り組んでいきましょう。
関連記事:子供がインフルエンザになった時の親の対応|風邪や似ている病気との違いについても解説
インフルエンザの予防はワクチン接種から
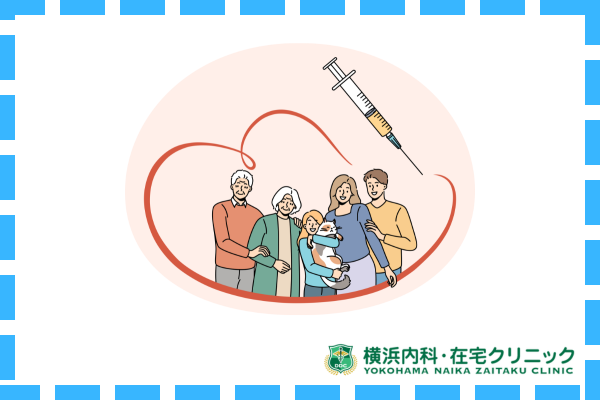
ワクチン概要
インフルエンザが流行する12月の前に、毎年10~11月に予防接種を受けることが推奨されています。
ワクチンは接種後2週間で効果が発揮され、その効果は3か月ほど持続します。
「その年に流行が予測される型」に対応するため、毎年の接種が必要です。
ワクチンの効果
ワクチンを接種したからといって、インフルエンザに必ずかからないというわけではありません。
ただ、発病を予防する効果は認められており、特に重症化の予防において効果が期待されています。
【研究で実証された予防効果】
高齢者(65歳以上)への効果
- 34~55%の発病予防効果(日本・全国調査)
- 死亡リスク82%減少(日本・医療機関データ)
- 集中治療室入室リスク26%減少
- 死亡率31%減少 (ニュージーランド・大規模臨床研究)
小児への効果
- 6歳未満:41~63%の発病予防
- 3歳未満:42~62%の発病予防 (複数の臨床研究の統合結果)
インフルエンザのワクチンは、特に以下の方々には積極的な接種をお勧めします。
- 重症化リスクが高い方
65歳以上の高齢者
乳幼児(特に2歳未満)
基礎疾患をお持ちの方 - 上記の方々と同居されているご家族
- 医療従事者・介護従事者
接種を行っても感染リスクは変わらないので、接種後も基本的な感染対策の継続が重要です!
予防接種は、個人の重症化予防だけでなく、社会全体の感染拡大防止にも貢献にもなります。
ご自身と大切な方々を守るため、かかりつけ医とご相談の上、適切な時期の接種をご検討ください。
日常でできるインフルエンザ予防方法

インフルエンザ予防において、先述したとおりワクチン接種を行っても感染リスクは変りません。
ワクチンだけに頼るのではなく、日常生活での対策も非常に重要と言えるでしょう。
以下の感染症対策に気を付けることで、感染を防ぐ効果が期待できます。
- 人混みに出ない
- 手洗い・うがい
- マスク着用
- 部屋の温度・湿度管理
- 十分な栄養補給と適度な運動
- 薄着の習慣
ここからは、これらの感染症対策のポイントを解説しましょう。
人混みに出ない
インフルエンザが流行している時期には、ショッピングセンターや繁華街など、不要不急の外出は避けたことをおすすめします。
どうしても外出が必要な際は以下のポイントを気をつけ外出しましょう。
- マスクを必ず着用
- できるだけ短時間で済ませる
- 混雑時間を避ける
手洗い・うがい
帰宅後は、まず手洗い・うがいを必ず行いましょう。
これはインフルエンザだけでなく、さまざまな感染症対策にも有効です。
手洗いを行う際は以下のポイントを気を付けることで、より効果があります。
- 石鹸を使用して、20秒以上かけて丁寧に洗う
- 指の間や爪の周りまで念入りに行う
- 流水で15秒以上かけて洗い流す
- 清潔なタオルで水分をしっかり拭き取る
マスク着用
人混みへの外出時には、マスクの着用が感染予防に効果的です。
中でも不織布マスクは最も効果が高く感染症対策におすすめです。
注意点として、マスクの裏返しに付けてしまうとマスクのすき間にウイルスなどが溜まりやすくなってしまいます。
裏表の確認や、上下の確認をしてあごや鼻を覆うようにすき間なく正しく着用しましょう。
部屋の温度・湿度管理
インフルエンザが流行する冬は、空気が乾燥しやすく、感染リスクが高まります。
空気が乾燥すると鼻やのどが乾燥し、免疫機能が低下してウイルスが活発になります。
さらに、温度が低いと血流が悪くなり、防御機能が低下するため、ウイルスに感染しやすいです。
冬の間は、暖房や加湿器を使って室内の温度と湿度を適切に管理することが大切です。
推奨温度は20~25℃、湿度は40%以上を保つよう心がけましょう。
十分な栄養補給と適度な運動
免疫力を高めるには、バランスの取れた食事と適度な運動が重要です。
ビタミンCは柑橘類や緑黄色野菜から、ビタミンB群は肉類や魚介類から積極的に摂取しましょう。
運動は無理のない範囲で続けることが大切です。
20~30分程度のウォーキングや軽いヨガなど、自分に合った運動を選びましょう。
薄着の習慣
体温調節機能を維持するために、適切な衣服管理が重要です。
基本的に薄着を心がけ、気温の変化に応じて調整できる重ね着スタイルがおすすめです。
寒い時期は必要な防寒対策をしつつ、室内では上着を脱ぐなど、環境に応じた調整を心がけましょう。
汗をかいた際は早めに着替えることで、体温管理を適切に保つことができます。
関連記事:インフルエンザワクチンにかかる費用や値段はどれくらい?メーカーの種類によって効果は変わる?
インフルエンザに予防におすすめ食べ物
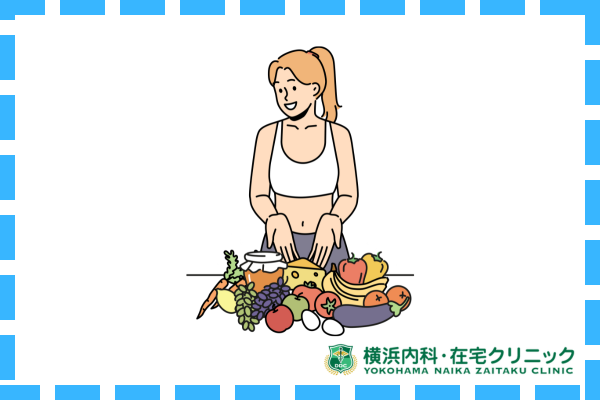
先述した通り、栄養はバランス良く摂取することで身体の免疫力を高めることが出来ます。
そのためにも下記の栄養素を含む食べ物を積極的に取り入れてみてください。
- たんぱく質
- ビタミンC
- ビタミンA
- 発酵食品
- 食物繊維
- 温かい食べ物
ここでは、各栄養素について詳しく解説します。
たんぱく質
たんぱく質は、免疫細胞の生成に不可欠な栄養素です。
効果的に免疫力を高めるには、「良質なたんぱく質」を含む食品を選ぶことが大切です。
良質なたんぱく質とは、アミノ酸がバランスよく含まれているものを指します。
以下の食品から、1日の目安量(成人で50~60g)を摂取することをおすすめします。
【おすすめの食品と特徴】
- 魚(サバ、サケなど)
- 脂肪の少ない肉(ささみ、もも肉など)
- 大豆製品(納豆、豆腐)
- 卵
- 乳製品(ヨーグルト、低脂肪牛乳)
【摂取のポイント】
たんぱく質自体の過剰摂取の心配は少なめですが、以下の点に注意が必要です。
- 肉類→脂肪の少ない部位を選択
- 魚類→青魚は良質な油が含まれているので積極的に摂取OK
- 大豆製品→加工品の場合は添加物に注意
- 乳製品→低脂肪タイプを活用
たんぱく質の1日の摂取目安は以下の通りです。
- 朝:卵1個+ヨーグルト
- 昼:大豆製品(納豆や豆腐)
- 夕:魚または肉(手のひらサイズ)
このように組み合わせることで、脂質を気にせず必要なたんぱく質を摂取できます。
ビタミンC
ビタミンCは、体の免疫機能を高め、風邪や感染症から身体を守る重要な栄養素です。
1日の推奨量(成人で100mg)を意識しながら、以下の食材を日々の食事に取り入れましょう。
ビタミンCが豊富な食材(100g当たりの含有量)
- アセロラ(1700mg)
- パプリカ(170mg)
- ブロッコリー(120mg)
- キウイ(69mg)
- 柑橘類(レモン50mg、オレンジ40mg)
ビタミンCは熱と水に弱い性質があるため、以下の摂取方法がおすすめです。
- 生食(サラダ、カットフルーツ)
- 飲み物(フレッシュジュース、スムージー)
- 加熱調理の場合は蒸し料理を選択
毎日継続的に摂取することで、年間を通じて安定した体調管理が期待できます。
特に、疲れを感じる時期や季節の変わり目には意識的な摂取を心がけましょう。
ビタミンA
ビタミンAは、私たちの身体の免疫機能を高める重要な栄養素です。
特に鼻やのどの粘膜を強化し、ウイルスの侵入を防ぐ働きがあります。
代表的なビタミンA豊富食品
- レバー(豚・鶏):最も豊富な供給源(100g当たり10000μg)
- ウナギ:蒲焼や白焼きで手軽に摂取可能
- 卵:毎日の食事で無理なく摂取できる
- 牛乳:カルシウムと一緒に効率よく摂取
- 緑黄色野菜:βカロテンの形で安全に摂取可能
ただし、レバーなどの動物性食品からのビタミンAは過剰摂取に注意が必要です。
1日の推奨量(成人で600~800μg)を大幅に超えないよう、週1~2回程度の摂取を心がけましょう。
緑黄色野菜からのビタミンAは体内で必要な分だけ変換されるため、積極的に摂取することをおすすめします。
発酵食品
発酵食品は、私たちの腸内環境を整え、免疫細胞をサポートする重要な役割を果たします。
発酵することによって微生物の働きに作られる過程で、栄養価が向上し、栄養が吸収されやすくなるメリットがあります。
さまざまな発酵食品には、体の代謝を促進してくれるビタミンB群や、腸内環境を整える乳酸菌や納豆菌が含まれています。
代表的な発酵食品には以下のようなものがあります。
- 味噌
- 納豆
- ヨーグルト
- チーズ
- キムチ
食物繊維
食物繊維は「人の消化酵素で消化できない物質」という特徴を持っています。
この性質により、腸内で特別な働きをし、便秘解消効果や血中コレステロールを下げる効果を発揮します。
食物繊維の摂取は、現代の食生活では不足しがちですが、白米を玄米に変えるなどの工夫で、手軽に摂取量を増やすことができます。
- ひじきや海苔などの海藻類
- ラズベリー、ブルーベリー
- しらたき、こんにゃく
- きくらげ、しいたけ(乾燥)
温かい食べ物
前述したように体温が下がると、それだけで免疫機能は低下してしまいます。
体温が1度下がると、免疫力は約30%も低下するとも言われています。
そのため、温かい食事で体温を保つことは、免疫力維持の基本です。
特に以下の食材は体を温める効果が高いとされています。
- 生姜:血行促進作用があり、体を内側から温めます
- 唐辛子:カプサイシンの働きで代謝を上げます
- ニンニク:アリシンという成分が血行を促進します
- ネギ類:辛み成分による発汗作用があります
- シナモン:血流を改善し、体を温める効果があります
温かい食べ物を効果的に取り入れるコツは、朝食を温かい味噌汁や飲み物から始めることです。
また、生で食べていた野菜を温野菜に変えたり、スープや鍋物を積極的に取り入れたりするのも良いでしょう。
ゆっくりと食べることで、より効果的に体温を維持することができます。
インフルエンザかも?病院受診のタイミング

インフルエンザかもしれないと感じた場合、発熱後12時間以上48時間以内の病院受診が望ましいです。
理由は2つあります。
まず1つ目は、発症から時間が経たないとウイルスが少なく、正しい検査結果が得られない可能性があるためです。
発熱から12時間以内での検査は、体内のウイルスが検査で陽性になる十分な数になっていないことがあります。
2つ目は抗インフルエンザ薬を正しく処方するためです。
タミフルやイナビルはウイルスの増殖を防ぐ役割を持っています。
48時間以上経過してしまうと、ウイルスが増殖しきってしまい、十分な効果が発揮できません。
この2つの理由から発症後(インフルエンザと思わしき症状が出てから)12時間以上48時間以内の受診が望ましいとされます。
ただし、症状が重篤な場合はすぐに病院を受診してください。
関連記事:インフルエンザの初期症状をチェック項目で解説!受診するタイミングは?
横浜内科・在宅クリニックでできる対応
当院ではインフルエンザワクチンの投与、診察から検査、イナビルやタミフルの処方まで対応することが可能です。
ワクチン接種ご希望の方はご予約が必要になりますので、あらかじめご予約ください。
また、自宅で検査をされた場合は、確定診断と薬の処方希望という方はオンライン診療も対応しています。
インフルエンザワクチン予約、発熱外来の診察予約、オンライン診療の予約の診察は以下の「WEB予約・オンライン診療予約はこちら」のボタンより行えます。
ご不明な点などございましたら、お気軽にクリニックへお問い合わせください。
まとめ
インフルエンザの予防とワクチンの接種は、高齢者の方や小児、持病のある方には特に必要です。
ですが、それ以外の方もインフルエンザの予防対策をすることで、重症化のリスクがある方への感染予防につながります。
まずは基本的な手洗いうがいを徹底し、人混みへ出る際はマスクを着用しましょう。
また、十分な休養と栄養バランスの良い食事を心がけ、体調管理に気を配ることで、効果的な予防が可能です。
参考文献
インフルエンザの感染を防ぐポイント 「手洗い」「マスク着用」「咳(せき)エチケット」
急な温度変化による咳やぜんそくに要注意!季節の変化によるアレルギーの原因と対策
健栄製薬|インフルエンザにかかったかも・・・病院へ行くタイミングはいつがいいの?

横浜内科・在宅クリニック 院長:朝岡 龍博 医師
『クリニックに関わる全ての人を幸せに』
『最後まで患者様と病気と向き合います』
【経歴】
・2016年 名古屋市立大学卒業、豊橋市民病院 初期研修医勤務
・2018年 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科
・2020年 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科
・2021年 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科
・2022年 西春内科・在宅クリニック 副院長
・2023年 横浜内科・在宅クリニック 院長
【資格】
・舌下免疫療法講習会修了
・厚生労働省 指定オンライン診療研修修了
・緩和ケア研修会修了
・難病指定医
・麻薬施用者
投稿者プロフィール
最新の投稿
 ブログ2026.01.30ワキガじゃないのに脇が臭い原因は?考えられる理由と改善のポイント
ブログ2026.01.30ワキガじゃないのに脇が臭い原因は?考えられる理由と改善のポイント お知らせ2026.01.28【腎不全と在宅患者の皮膚トラブルについて】ケアマネ勉強会のお知らせ
お知らせ2026.01.28【腎不全と在宅患者の皮膚トラブルについて】ケアマネ勉強会のお知らせ お知らせ2026.01.241/30(金)外来診療休診のお知らせ
お知らせ2026.01.241/30(金)外来診療休診のお知らせ お知らせ2026.01.10午後の外来診療時間変更について
お知らせ2026.01.10午後の外来診療時間変更について