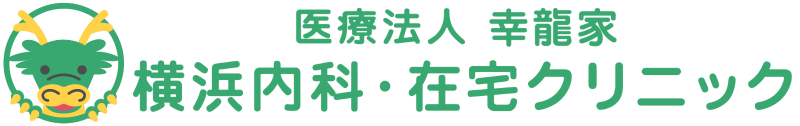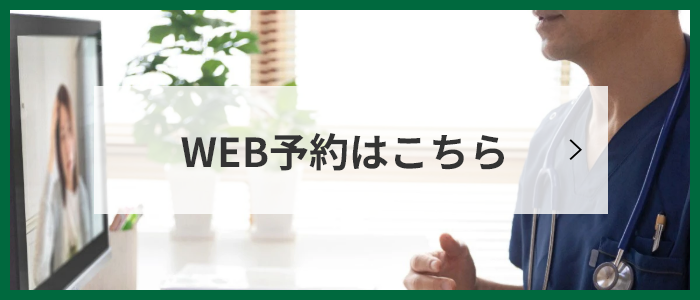ウイルス性胃腸炎の症状で下痢のみが起きる理由|何日で治る?

吐き気や嘔吐、腹痛などの症状を起こすウイルス性胃腸炎という病気をご存知でしょうか。
ウイルス性胃腸炎とはウイルスなどに感染することによって腹部の症状を起こしてしまう、日常的によくある病気の1つです。
しかし、ウイルス性胃腸炎はどのような病気で原因や症状にはどういったものがあるのでしょうか。
この記事ではウイルス性胃腸炎の原因や感染経路、症状などについて解説します。
ぜひ最後までご覧になって、参考にしてみてください。
- 1. ウイルス性胃腸炎の原因・感染経路
- 1.1. ノロウイルス
- 1.2. ロタウイルス
- 1.3. その他のウイルス
- 2. ウイルス性胃腸炎の潜伏期間
- 3. ウイルス性胃腸炎の症状
- 3.1. 吐き気と嘔吐
- 3.2. 下痢
- 3.3. 腹痛と腹部不快感
- 3.4. 発熱
- 3.5. 全身の倦怠感
- 4. ウイルス性胃腸炎で下痢のみが起きてしまう理由
- 5. ウイルス性胃腸炎はうつる可能性がある?
- 6. ウイルス性胃腸炎になったら仕事は何日休むべき?
- 7. ウイルス性胃腸炎になったときの食事について
- 8. ウイルス性胃腸炎の治し方・何日で治る?
- 9. 横浜内科・在宅クリニックでの対応方法
- 10. 横浜内科・在宅クリニック院長 朝岡が実際に経験した例!
- 11. まとめ
ウイルス性胃腸炎の原因・感染経路
ウイルス性胃腸炎を起こす代表的なウイルスにはどんなものがあるのでしょうか。
代表的なウイルスとして以下などのウイルスが挙げられます。
- ノロウイルス
- ロタウイルス
- その他
アデノウイルス・アストロウイルスなど
各ウイルスの特徴とその感染経路について解説していきます。
ノロウイルス
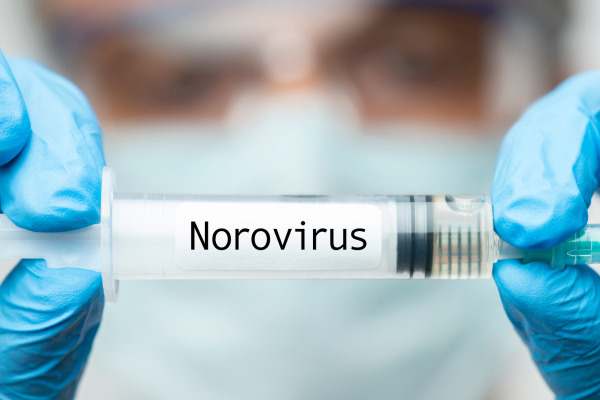
ノロウイルスは、主にヒトに感染し、胃腸炎を引き起こすことで知られています。
ウイルスは感染者の便や嘔吐物中に多く存在し、直接触れた場合や飲食物を摂取した場合に広がります。
感染源としては、以下などが代表的です。
- 感染者の食品
- 感染者の糞便・吐物
- 感染者の糞便・吐物が付着した物品類
- 牡蠣などの貝類
ロタウイルス
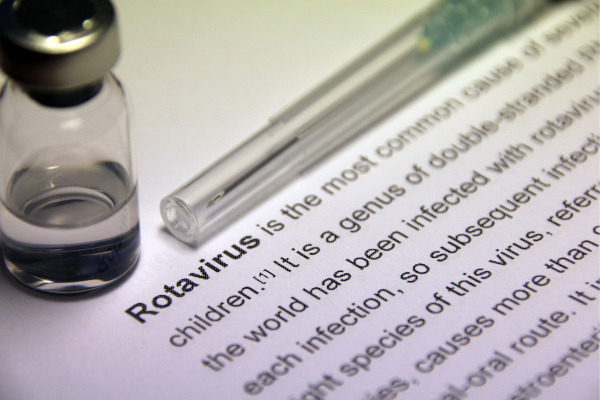
ロタウイルスも、主にヒトに感染し、胃腸炎を引き起こすウイルスです。
感染者の便や嘔吐物中に存在し、感染は感染者との接触や感染者の排泄物に触れた後にウイルスが付着することによって広がります。
特に乳幼児や幼児は感染しやすく、集団感染が発生することがあります。
その他のウイルス

ノロウイルスとロタウイルス以外にも、アデノウイルスやアストロウイルスなど、さまざまなウイルスがウイルス性胃腸炎を引き起こす原因となります。
これらのウイルスも、感染者の便や嘔吐物を介して感染が広がります。
感染経路としては、ウイルスが食品や水といった経口摂取物に直接付着し、それを摂取することによる感染が一般的です。
また、感染者の手や汚染された表面にウイルスが付着し、その後手や食品に触れることで感染することもあります。
さらに、感染者との密接な接触によっても感染が広がることがあります。
予防策としては、手洗いや衛生的な習慣の実践が重要です。
特にトイレ使用後や食事前、食品の調理前など、適切なタイミングでの手洗いを行うことが重要です。
また、感染者との接触を避けることや、感染者がいる場所での食事や飲み物の摂取を避けることも推奨されます。
公共の場での手指の消毒や、食品の十分な加熱も感染予防の重要な対策となります。
関連記事:【子供の下痢】ロタウィルス感染症の症状や感染経路について解説!予防接種は必要?
関連記事:咽頭結膜熱(プール熱)ってどんな病気?大人もかかる?流行性角結膜炎との違いも解説!
ウイルス性胃腸炎の潜伏期間

潜伏期間とは体にウイルスが感染して、ウイルスが増殖しているものの、症状がまだ出ていない時期を指します。
ウイルス性胃腸炎の潜伏期間は原因となるウイルスによって異なります。
原因となるウイルス毎に潜伏期間の目安は以下の通りです。
| ウイルス | 潜伏期間 |
| ノロウイルス | 1〜2日程度 |
| ロタウイルス | 1〜3日程度 |
| アデノウイルス | 2〜10日程度 |
これらは一般的な期間ですので、症状が出現するまでの期間には個人差があります。
また、症状が現れる前から感染力を持つこともあるので、感染予防のためにも普段から手洗い、手指衛生に気を付けることが大切です。
ウイルス性胃腸炎の症状
ウイルス性胃腸炎は、感染したウイルスによって胃腸に炎症を起こす病気です。
一般的な症状は以下のようになりますが、個人によって症状の程度や経過は異なる場合があります。
- 吐き気と嘔吐
- 下痢
- 腹痛と腹部不快感
- 発熱
- 全身の倦怠感
これらの一般的な症状について詳しく解説しましょう。
吐き気と嘔吐

吐き気や嘔吐はウイルス性胃腸炎でよく起こる症状です。
嘔吐の回数が多い場合や、吐き気で水分が摂取できない状態が続くと脱水症状を起こしてしまうこともあります。
関連記事:食中毒かもしれない症状を解説!うつる可能性や対処方法は?
下痢

水っぽい便や軟便が現れます。
下痢は頻繁で、水のような便が大量に出ます。
一般的に血便はウイルス性の胃腸炎では起こりません。
しかし、痔核などがある方は何度も排便することによって便に血が混じる場合もあります。
関連記事:腹痛と下痢が続く原因|コロナの可能性は?治し方や病院での対処法を解説
腹痛と腹部不快感

腹痛や腹部不快感も多い症状の一つです。
痛みは軽度から中程度のもので、腹部に全体的に生じることが特徴です。
腹部の特定の箇所が痛い場合にはウイルス性胃腸炎以外の別の病気の可能性があります。
関連記事: 急性腸炎ってなに?ストレスが関係する?原因や症状について
関連記事:食中毒かもしれない症状を解説!うつる可能性や対処方法は?
発熱

体に炎症起こる結果として、発熱が生じることがあります。
一般的に38℃以上の高熱まででることは少なく、解熱剤やクーリングで対応できることがほとんどです。
関連記事:発熱の基準は何度から?外来に行くべき目安やよくある症状を解説
全身の倦怠感

疲労感や体のだるさが現れることがあります。
これらの症状がそろっている場合には臨床的にウイルス性胃腸炎と診断することができます。
しかし、発熱と腹部の特定の部位の痛みなどの場合には虫垂炎や胆嚢炎などの別の病気の可能性もあります。
注意して症状を観察することが大切です。
ウイルス性胃腸炎で下痢のみが起きてしまう理由

ウイルス性胃腸炎にかかった多くの方は下痢のほかに、嘔気や嘔吐、腹痛などの症状を起こします。
しかし、中には下痢のみの症状の方もいます。
下痢はウイルスが腸の細胞に感染した結果、炎症を引き起こすことで腸からの分泌液が増加し、運動が亢進※1(こうしん)することで起こります。
※1亢進…高い度合に(まで)進むこと
嘔気や嘔吐、腹痛の現れ方には個人差があり、感染した方の中には症状が下痢だけという場合もあるのです。
ウイルス性胃腸炎はうつる可能性がある?

ウイルス性胃腸炎は感染性のある病気なので、他の人に感染する可能性があります。
下痢や嘔吐などの症状がある時にはウイルスが排出されています。
感染した人との接触は可能な限り避けて、手洗いやアルコールでの手指消毒などを徹底することが大切です。
また、特にノロウイルスでは、症状が消失した後も3〜7日間ほど患者の便中にウイルスが排出されます。
症状がなくなった後でも感染対策をしっかりと行うことが重要です。
関連記事:大人のウイルス性・細菌性の胃腸炎の原因や症状、改善方法|嘔吐や下痢の原因?
ウイルス性胃腸炎になったら仕事は何日休むべき?

ウイルス性胃腸炎になったときの休職について、法律上の出勤停止日数は定められていません。
しかし、会社ごとに定める「就業規則」に日数の規定がある場合があるので、必ず職場に確認するようにしてください。
原則として、嘔気や嘔吐、腹痛、下痢などの症状が続いている間は業務に支障があるので休業することが望ましいと言えます。
その後の復帰時期については一概には言えません。
しかし、ノロウイルスでは、発症から1週間程度はノロウイルスが排出されています。
飲食業では1週間程度は出勤停止にする所が多くみられます。
ウイルス性胃腸炎になったときの食事について

ウイルス性胃腸炎になってしまった時に注意する食事について解説していきます。
まず脱水症状にならないように水分を十分に摂取するようにしてください。
ウイルス性胃腸炎では嘔吐や下痢によって水分が失われやすい状況にあります。
嘔気のため水分摂取も難しい場合もありますが、こまめに水を飲むことが大切です。
また、水だけでは電解質が補給できないので、電解質が入ったOS-1などの経口補水液を選びましょう。
食事については消化吸収をしやすいお粥や果物などの摂取が有効です。
逆に、脂っこい食事や香辛料の入った食事、カフェインやアルコールなどの刺激の強い食品は控えるようにしましょう。
関連記事:高血圧の原因になりやすい食事や食べてはいけないものとは?
ウイルス性胃腸炎の治し方・何日で治る?

ウイルス性胃腸炎になった時には脱水症にならないように水分を十分に摂取しながら、消化にやさしい食事を取るようにしましょう。
またビフィズス菌や乳酸菌などが含まれた整腸剤は早めに症状を和らげるのに役立ちます。
整腸剤は市販もされていますし、病院を受診した際にも処方してもらうことも可能です。
これらの対応でもともと健康な方であれば1週間程度で自然によくなります。
しかし、小児や高齢者、持病を持っている方では脱水症になってしまう方もいらっしゃいます。
そのような場合には病院での点滴や病院受診も難しいほど辛いときには往診の利用も検討してみてください。
横浜内科・在宅クリニックでの対応方法
ウイルス性胃腸炎は軽い病気と考えられがちですが、思いがけず悪化してしまう場合があります。
横浜内科・在宅クリニックでは丁寧な問診、診察を行い、診断を行います。
必要があれば採血などで脱水の評価、点滴での加療をおこないます。
ご本人、ご家族と相談をしてご納得のいける治療を提供できるように対応いたしますので、お困りの際にはいつでもご相談ください。
横浜内科・在宅クリニック院長 朝岡が実際に経験した例!
40代の男の方で、繰り返す下痢を主訴に病院に来られた方がいました。
その方は何度も下痢を繰り返しており、嘔気もあったため水分摂取がほとんど出来ていなかったようです。
すぐに点滴を行い、心臓を超音波検査で確認したところ、著名な脱水を認めておりました。
成人の方でも繰り返す大量の下痢にて脱水を起こすのだと経験しました。
その方はノロウィルスによってウィルス性胃腸炎を引き起こしていました。
まとめ
今回は、ウイルス性胃腸炎の原因や感染経路、症状などについて解説しました。
ウイルス性胃腸炎はウイルスに感染することによって胃腸に炎症を起こし、嘔気、嘔吐や腹痛、下痢を起こす疾患です。
通常は数日から1週間程度で特別な治療をせずとも改善します。
しかし、中には脱水症状のため状態が悪化してしまう方もいます。
心配な症状がある時には、ぜひお気軽にご相談してください。
参考文献
‣ノロウイルス感染症とは|国立感染症研究所
‣ロタウイルス感染性胃腸炎とは|国立感染症研究所
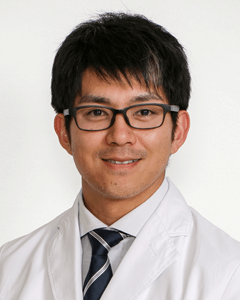
整形外科医 Dr.三浦隆徳

横浜内科・在宅クリニック 理事長:朝岡 龍博 医師
『クリニックに関わる全ての人を幸せに』
『最後まで患者様と病気と向き合います』
【経歴】
・2016年 名古屋市立大学卒業、豊橋市民病院 初期研修医勤務
・2018年 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科
・2020年 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科
・2021年 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科
・2022年 西春内科・在宅クリニック 副院長
・2023年 横浜内科・在宅クリニック 院長
・2025年 医療法人 幸龍家 理事長
【資格】
・舌下免疫療法講習会修了
・厚生労働省 指定オンライン診療研修修了
・緩和ケア研修会修了
・難病指定医
・麻薬施用者