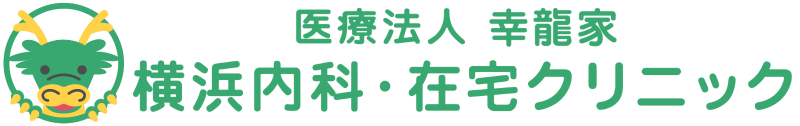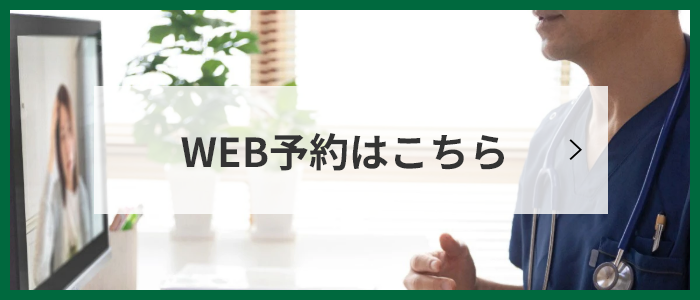口内炎に効くおすすめの市販薬ランキング|選ぶときのポイントや治らない場合の対応は?
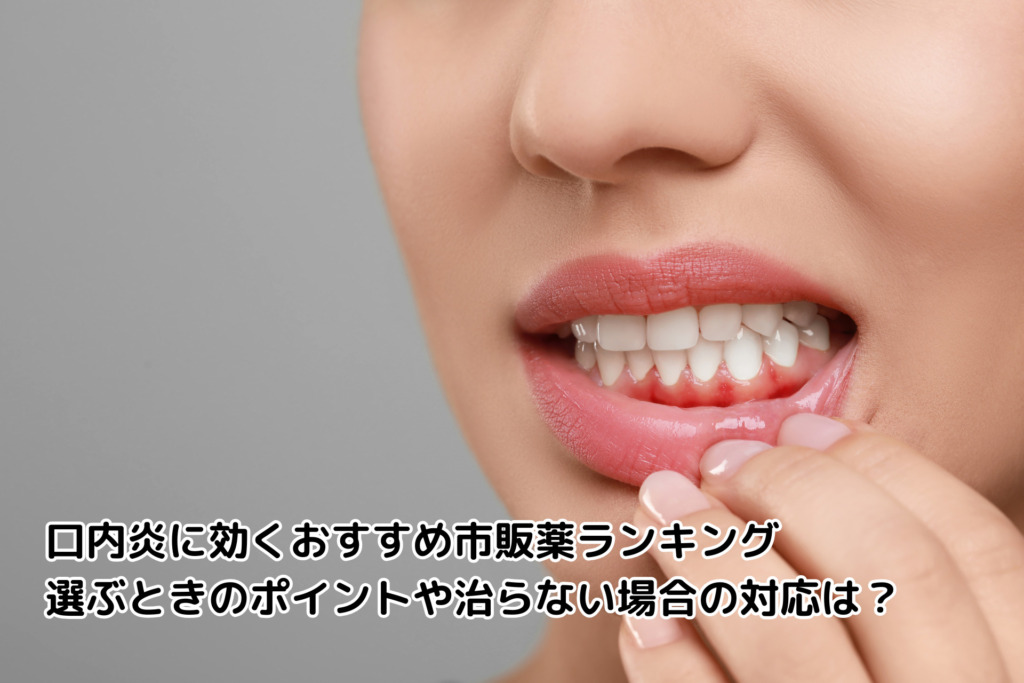
食事や会話をするたびに痛みを感じ、日常生活に不快感を与える厄介なトラブルの口内炎。
できやすい方はいても、できたことがないという方はいないのではないでしょうか?
放っておいても自然に治癒はしますが、症状が長引いて痛みが続くときは早く治したいですよね。
口内炎を早く治したいときには、やはり市販薬を使用するのがおすすめです。
この記事では、口内炎に効果的な市販薬をランキング形式で紹介し、それぞれの特徴、選び方のポイントなどを解説していきます。
- 1. 口内炎に効くおすすめの市販薬ランキング
- 1.1. 1位:トラフル軟膏PROクイック
- 1.2. 2位:アフタッチA
- 1.3. 位:オルテクサー口腔用軟膏
- 1.4. 4位:トラフル軟膏
- 1.5. 5位:口内炎パッチ大正A
- 2. 口内炎の薬を選ぶときのポイント
- 2.1. 口内炎の種類に合わせた薬選び
- 2.1.1. アフタ性口内炎
- 2.1.2. カタル性口内炎
- 2.1.3. ウイルス性口内炎・真菌性口内炎
- 2.2. 長期的な症状には非ステロイド系を選ぶ
- 2.3. 年齢に合わせた薬選び
- 3. そもそも口内炎ができてしまう理由とは?
- 3.1. 栄養バランスの乱れ
- 3.2. ストレス・睡眠不足
- 3.3. 口内の乾燥
- 3.4. 細菌増殖・ウイルス感染
- 3.5. 病気や薬の影響
- 3.6. 歯磨きの仕方
- 4. 口内炎を予防するためのセルフケア
- 4.1. 食生活の改善と栄養補給
- 4.2. 生活習慣を見直してストレスを減らす
- 4.3. 口内を清潔に保つためのケア
- 5. 市販薬を試したけど口内炎が治らないときはどうする?
- 6. 横浜内科・在宅クリニックでできること
- 7. まとめ
口内炎に効くおすすめの市販薬ランキング
ここではおすすめの市販薬をランキング形式で紹介していきます。
商品の特徴なども解説していくのでご覧ください。
1位:トラフル軟膏PROクイック

即効性が高いステロイド系の口内炎治療薬です。
主成分の「トリアムシノロンアセトニド」が炎症を効果的に抑えて、患部を保護する膜を形成して外部刺激から口内炎を守り、痛みを軽減します。
チューブタイプなので使いやすく、少量で広範囲に塗布することが可能で、即効性があり強い炎症や痛みをすぐに軽減可能です。
ステロイド系のため長期間の使用は副作用のリスクがあり、塗布時は唾液で流れやすいので、塗布後は少しの間安静にする必要があります。
強力な薬のため、子どもや妊娠中の方が使用するのは注意が必要です。
2位:アフタッチA

アフタッチAは患部に貼るタイプの治療薬です。
主成分の「トリアムシノロンアセトニド」が炎症を抑えつつ外部刺激を遮断します。
食事中や会話の際の痛みを大幅に軽減でき、薬が患部を覆うため、外的要因によるさらなる悪化を防ぐことができます。
長時間効果が持続し塗り直しなどの必要がなく、貼るタイプでありながら溶けてなくなるので、はがれたものを捨てなくてもよいのが利点です。
初めて使う人には貼り付けるのが難しい場合があり、位置がずれると効果が弱まるため注意が必要です。
サイズが決まっているので小さな患部には使いやすいですが、大きな口内炎には不向きと言えます。
位:オルテクサー口腔用軟膏

ステロイド成分「トリアムシノロンアセトニド」を含む軟膏タイプの薬で、患部に塗布すると粘膜に密着し、強い抗炎症作用を発揮します。
炎症を効果的に抑える強力な作用があり、少量で効果が高いので、コストパフォーマンスに優れています。
患部への密着性が高く、長時間効果が持続するのも特徴で、口内炎が広がりやすい方や、炎症がひどい場合に効果的です。
ステロイド成分を使用しているため、長期的な使用や広範囲の塗布は避けましょう。
塗布後に唾液で流れる場合があるため、使用後はしばらく安静が必要です。
人によっては、塗布直後に刺激を感じることがあります。
4位:トラフル軟膏

非ステロイド系の抗炎症成分「アズレンスルホン酸ナトリウム」を含む軟膏で、ステロイドを避けたい方でも使用できる低刺激タイプです。
非ステロイド系のため刺激が少なく、子どもや敏感肌の方でも安心して使用が可能で、抗炎症作用だけでなく、患部を保護する効果も期待できます。
ステロイド系薬に比べると即効性に劣り、重度の症状には効果が不十分な場合があります。
軟膏の粘度が高いため、塗布が難しいと感じることがありますが、軽度の口内炎や再発防止のためのケアに最適な薬です。
5位:口内炎パッチ大正A

薄型のパッチが患部を保護しつつ、薬用成分が長時間にわたって患部に浸透します。
薄くて目立たないため、外出中でも使いやすく、パッチの固定力が強いので口内でも剥がれにくく、食事中や会話中の摩擦や痛みを軽減します。
仕事中や外出先で口内炎が気になる方におすすめです。
貼り直しができないので失敗すると再利用できず、サイズが決まっているため大きな口内炎には不向きです。
関連記事:子どもの虫歯について|できやすい場所や予防法を解説
口内炎の薬を選ぶときのポイント

口内炎の種類に合わせた薬選び
原因の違いで出てくる症状も変わり、以下の種類に分かれています。
アフタ性口内炎
ストレスや栄養不足が原因で、小さな白色または黄色の潰瘍ができ、周囲が赤く腫れる一般的な口内炎の症状です。
痛みを伴い、食事や会話に支障をきたすことも多いです。
カタル性口内炎
口腔内が不衛生だったり、刺激物や入れ歯などで、口の中が赤く腫れて広範囲に炎症が起こります。
粘膜が荒れたり、ただれたりして痛みを伴う症状です。
ウイルス性口内炎・真菌性口内炎
発熱を伴うことが多く、水疱や潰瘍が口腔内に広がります。
乳幼児や免疫力が低下している場合に発生しやすいです。
起きている症状や原因に合わせて使用する薬を選ぶことが重要です。
長期的な症状には非ステロイド系を選ぶ
ステロイド成分は短期的には効果が高いものですが、長期的に使用すると局所的に免疫が低下したり、組織の萎縮などの副作用が起こる可能性があります。
再発を繰り返す、長期的に炎症を起こしているなど慢性的な場合は、非ステロイド系の薬を選ぶとよいでしょう。
年齢に合わせた薬選び
乳幼児や子ども、高齢の方には刺激が少ない非ステロイド系のものがおすすめです。
特に乳幼児は飲み込んでしまっても大丈夫な軟膏・ジェルタイプを選びましょう。
そもそも口内炎ができてしまう理由とは?

口内炎にはさまざまな原因が考えられます。
ここからは、口内炎の原因についてご紹介しましょう。
栄養バランスの乱れ
主な原因として以下などの栄養素の不足が挙げられます。
- ビタミンB2
- ビタミンB6
- ビタミンC
- 鉄分
- 亜鉛
偏った食事などで栄養が不足すると、粘膜の修復能力が低下して、炎症が発生しやすくなります。
ストレス・睡眠不足
精神的・身体的なストレスや寝不足が続くと免疫力が低下し、細菌やウイルスへの抵抗力が弱まって炎症が起こり、口内炎ができやすくなります。
口内の乾燥
加齢や薬剤の影響で唾液が減少して口腔内が乾燥すると、殺菌作用が低下して細菌が増えやすくなって炎症を起こし、口内炎ができやすくなります。
細菌増殖・ウイルス感染
カンジダ菌やヘルペスウイルス・コクサッキーウイルスなどが原因の感染症で、口腔内で増殖することで炎症や潰瘍が発生します。
この際にできる口内炎が、ウイルス性口内炎・真菌性口内炎です。
病気や薬の影響
以下などの疾患や、抗がん剤治療による免疫不全があると口内炎ができやすくなります。
- ベーチェット病
- クローン病
- 潰瘍性大腸炎
- 糖尿病
他にも、抗炎症薬・抗菌薬の使用で粘膜が損傷しやすくなると、口内炎が発生します。
歯磨きの仕方
硬めの歯ブラシを使用したり、強い力で磨くことで口内に傷ができると、治癒する過程で炎症が起きて口内炎になります。
歯磨きが不十分だと、細菌の増殖や口腔内の汚れで炎症を起こします。
歯磨きの仕方ではなく、歯磨き粉に含まれている成分へのアレルギー反応の可能性もあるので注意が必要です。
関連記事:口唇ヘルペスを最短で治すには?おすすめの市販薬を紹介!
口内炎を予防するためのセルフケア
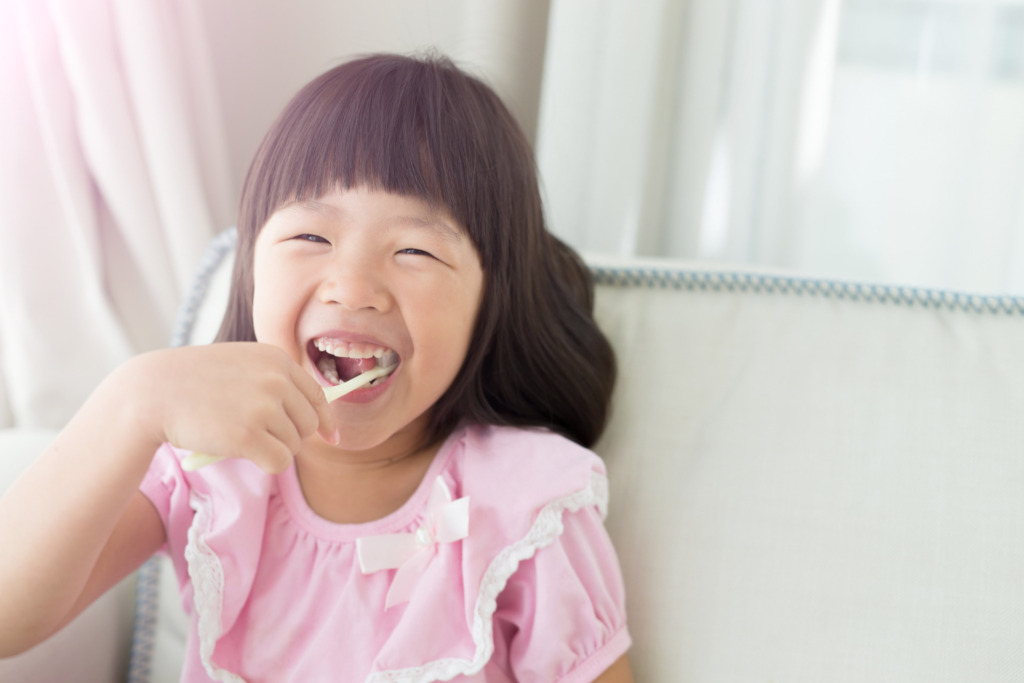
口内炎を予防するには、いくつかポイントがあります。
正しいセルフケアを用いて、口内の健康を保ちましょう。
食生活の改善と栄養補給
偏った食事によって、足りない栄養素があると口内炎ができやすくなります。
以下などの摂取で、口内炎ができにくくなります。
- 豚肉や卵に含まれるビタミンB群
- 柑橘類に多く含まれるビタミンC
- レバーや赤身の肉に多い鉄分
- 牛肉や豆類に多い亜鉛
他にも辛い食べ物や熱い飲み物は、粘膜を刺激して傷つけることもあるので、口内炎ができやすい方は控えた方がよいでしょう。
唾液の分泌を促すために、こまめに水を飲んで乾燥を防ぐのも重要です。
生活習慣を見直してストレスを減らす
精神的・身体的なストレスがあると口内炎ができやすい体質になります。
口内炎ができやすくなる原因のストレスを減らすためには、生活習慣の見直しが必要です。
まずは毎日決まった時間に起床・就寝し、生活リズムを整え、十分な睡眠時間を確保することで、身体の回復力を高めます。
趣味の時間やリラックスできる時間を作るのも、ストレスを減らすのに効果的です。
さらにウォーキングやストレッチなど、適度な運動を行うことで血行が良くなり、免疫力の向上につながります。
口内を清潔に保つためのケア
柔らかめの歯ブラシを使って、歯や歯茎を傷つけないようにし、食後や就寝前に歯磨きをするのを忘れないようにしましょう。
口内の細菌を減らすためにうがい薬を使用しますが、うがい薬がなければ水でうがいするのも効果があります。
口内を清潔に保つためにも、定期的に歯科検診をうけて虫歯の確認や、歯石の除去をするのも重要です。
唾液が少ない方であれば、ガムやタブレットを嚙むことで分泌を促すことができ、口内の乾燥を防ぐことが可能です。
市販薬を試したけど口内炎が治らないときはどうする?

市販薬で治らなかったり、痛みが続く場合は、医療機関での治療が必要になる可能性があります。
医療機関受診の目安として、以下などが挙げられます。
- 2週間以上治らない
- 痛みが強く治まらない
- 潰瘍が増えたり出血したりする
- 発熱や倦怠感を伴う
- 再発を繰り返す
こういった症状が1つでもあったら早急に医療機関を受診をしたほうがよいでしょう。
歯科などで口腔内の傷や粘膜の状態確認、内科などで血液検査やウイルス感染の有無などを調べることが可能です。
自己免疫疾患や胃腸の不調、ウイルスの感染症、ガンの可能性もあるので、自己判断せずに医療機関を受診して、適切な治療を受けることが重要です。
関連記事:手足口病は大人にもうつる?症状や潜伏期間を徹底解説
横浜内科・在宅クリニックでできること
横浜内科・在宅クリニックでは、口内炎の診察、薬の処方や必要に応じた検査などを提供することが可能です。
専門医の診察や、手術などの治療が必要な場合は紹介状を作成します。
気になる症状や、さきほどご紹介した受診目安に該当する場合はお気軽にご相談ください。
まとめ
いつの間にかできてしまう口内炎ですが、適切な薬を選び、セルフケアを行うことで症状を和らげることが可能です。
それでも症状が治らない場合は早めに医療機関の受診が必要です。
口内炎ができやすい方は、この記事を参考にして口内炎対策を始めましょう!

横浜内科・在宅クリニック 院長:朝岡 龍博 医師
『クリニックに関わる全ての人を幸せに』
『最後まで患者様と病気と向き合います』
【経歴】
・2016年 名古屋市立大学卒業、豊橋市民病院 初期研修医勤務
・2018年 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科
・2020年 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科
・2021年 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科
・2022年 西春内科・在宅クリニック 副院長
・2023年 横浜内科・在宅クリニック 院長
【資格】
・舌下免疫療法講習会修了
・厚生労働省 指定オンライン診療研修修了
・緩和ケア研修会修了
・難病指定医
・麻薬施用者