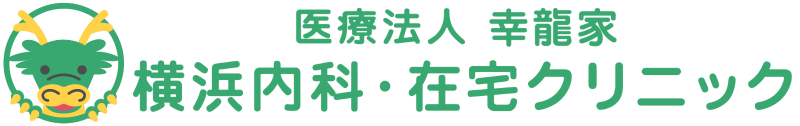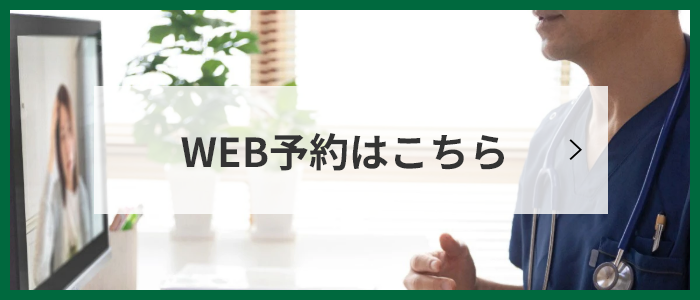【子どもの喘息】小児気管支喘息とは?悪化してしまう原因や発作が出た時に楽になる方法
季節の変わり目や秋から冬にかけて、子どもにとっては風邪を引きやすい時期ですよね。
子どもは気管支が細く、風邪の後などにゼイゼイしやすいと言われています。
その中で一定の割合で子どもの気管支喘息である小児気管支喘息の子が混ざっているのです。
小児気管支炎とは名前の通り“子どもの気管支喘息”ですが、大人の気管支喘息とは発症原因や経過に少し違いがあるため、医学の中では別ものとして分類されています。
今回は、そんな小児気管支喘息についてわかりやすく解説していきますね。
少しでも親御さんや患児のお子さんの不安解消になればと思います。
小児気管支喘息の症状
小児気管支喘息は、気管支が炎症を起こすことで症状が出ます。
大きな症状は、炎症で気管支が狭くなることで起こる、息を吸ったときの「ゼイゼイ」「ヒュウウヒュウ」です。
喘息発作には、以下の特徴があります。
- 夜間から朝型に出やすい
- 苦しくて横になっていられず、体を起こしていると楽になる(起坐呼吸)
風邪を引いた後に毎度咳が長引いて、息を吸った時にゼイゼイヒュウヒュウすることもあります。
このような症状の繰り返しがある場合には、気管支喘息を疑います。
ゼイゼイして息が苦しくなり、大きく息をしようとして小鼻がピクピク開いたり、首や肩で息をしていたりする場合には、呼吸はかなり苦しいというサインです。
息切れして会話ができない場合、急性が高い症状です。
小さいお子さんは自分からなかなか苦しいとは言えません、すぐに病院を受診しましょう。
関連記事:子供がインフルエンザになった時の親の対応|風邪や似ている病気との違いについても解説
小児気管支喘息が悪化する原因
小児気管支喘息は、アレルギーの要素が大きいです。
アレルギーの原因になる以下などで気管支が刺激されて発作が起こったり、症状が悪化する可能性があります。
- ダニ
- ほこり
- タバコや線香の煙
- 犬や猫の毛
- 冬の冷たく乾燥した空気や運動
小児気管支喘息と成人気管支喘息の違い
小児気管支喘息は、アレルギー物質が原因であることが多く、その他のアレルギー疾患であるアトピー性皮膚炎や食物アレルギーを合併することがあります。
アトピー性皮膚炎の悪化が小児気管支喘息の悪化に関係しているなど、アレルギー同士が影響しあうことをアレルギーマーチと呼び、小児のアレルギー疾患の特徴になります。
また、遺伝性の要素があることも多く、ご両親がアトピー性皮膚炎や気管支喘息であると、その子どもも小児気管支喘息などのアレルギー疾患を起こしやすくなります。
一方、成人になって症状がでてきた成人気管支喘息は、明らかなアレルギー物質がないか特定できないにもかかわらず、喘息の症状が出てきます。
アトピー性皮膚炎やその他のアレルギー疾患との関連もないことが特徴的です。
また、基本的には気管支喘息は発作を繰り返す慢性的な疾患ですが、治り方にも違いがあります。
小児気管支喘息は大きく分けて3つのタイプがあるといわれています。
- 一時的にゼイゼイする、喘鳴
- アレルギーが関係しない喘鳴
- アレルギーが関連した喘息
小児は気管支が細く、痰などの分泌物が増えると喘息でなくでもゼイゼイすることがあります。
特に2歳以下での気管支喘息の診断は非常に難しく、ゼイゼイする症状のことをまとめて喘鳴(ぜんめい)と表現します。
成長に伴って気管支も大きくなるため、喘鳴は起こりにくくなり、自然と改善します。
①、②のタイプの喘鳴は成長とともに自然に改善してしまうのです。
③のタイプのいわゆる本当の小児気管支喘息は自然に改善することが少ないため、症状に合わせた治療が必要になります。
成人の場合には、このように詳しい原因やメカニズムがはっきりわかっていません。
小児と比べると成長とともに自然に改善することは少ないため、症状がある場合には放置せずに治療を行うことが重要です。
小児気管支息の発作の対処法
喘息の発作が出た場合、手元に処方された吸入薬があれば、まずはそちらを使いましょう。
吸入薬を使っても症状が改善しない場合には、すぐに病院を受診してください。
軽い発作で飲み物を飲めそうなほどであれば、体を起こして水分を少しづつ飲ませましょう。
喉が潤うと、症状が改善することがあります。
ただし、むせてしまう場合などには無理に飲ませない方が良いでしょう。
体を起こした方が息がしやすいので、背中に枕などを入れて起こしてあげると良いかもしれません。
ただし、発作があって眠れない場合には、やはり病院受診が必要です。
小児気管支喘息の治療
小児気管支喘息の治療は大きく分けて、3つあります。
- 喘息発作が出た時に治す治療(発作治療)
- 気管支の炎症を抑える治療(抗炎症治療)
- ダニやほこりを減らして喘息を起こりにくくする治療(環境整備)
発作治療
まず発作が出てしまった時の治療としては吸入薬と張り薬があります。
喘息の発作が起こると、気管支の周りの平滑筋という筋肉が収縮し気管支が狭くなります。
気管支の平滑筋は意識的に動かすことができない自立神経で支配されており、交感神経を刺激すると平滑筋がゆるんで気管支は拡張します。
その作用を応用して、β刺激薬という薬を使うと気管支が拡張し、喘息発作の症状が緩和します。
吸入薬と貼付薬があり、年齢などに合わせて使い分けをしていきます。
抗炎症治療
発作が起こっていない場合、気管支炎の子どもの気管支ではアレルギー性の炎症が起こっています。
この炎症を改善してあげることで、発作も起こしにくくなります。
薬としては吸入ステロイド薬とロイコトリエン受容体拮抗薬があります。
ステロイドは炎症を強く抑える作用があり、直接気管支に薬剤が届くように細かい粉や霧状になったステロイドを吸入することで治療効果を得ることができます。
かつては点滴や錠剤でステロイドを飲んで治療していましたが、ステロイドの副作用である免疫力低下や血糖値の上昇、皮膚が薄くなるなどが問題になっていました。
研究が進み、吸入薬のステロイドの方が気管支喘息の気道の炎症を抑えるのに有効であり、かつ、副作用も100分の1にすることができることが分かりました。
現在では、ステロイドの飲み薬は最終手段の治療法になっています。
ロイコトリエン受容体拮抗薬とは、気管支を収縮する作用のある炎症物質のロイコトリエンと受容体を取り合うことで、気管支収縮を抑える作用があります。
飲み薬の治療薬になり、気管支喘息の症状が軽いうちから初めて長期的に飲むことで効果を表します。
環境整備
環境整備には以下がポイントになります。
- 寝具や寝室のダニ、埃がたまらないように定期的に掃除をする。
- タバコの煙で発作が誘発されるため、家族は禁煙をする。
- 犬や猫の毛を避けるか、すでに飼っている場合にはこまめに掃除をして毛が残らないようにする。
- 湿度を40~60%ほどに適切に保つ。湿度40%以下では発作が起こりやすく、湿度60%以上だとダニが繁殖しやすくなる。
以上、気管支喘息の治療法はこの3本柱で成り立っていますが、気管支喘息の発作の程度によって治療薬の選択肢が変わってきます。
気管支喘息の重症度は発作の頻度とその強さで決まります。
- 間欠型
軽い症状が数年に数回生じるくらいで、短期間で症状が改善するもの - 軽症持続型
軽い症状が月1回以上、週1回未満、症状は短期間で改善するもの - 中等症持続型
軽い症状が週1回以上、毎日ではないが、時に中等度から大発作になる - 重症持続型
毎日症状があり、週1、2回は大きな発作になる
喘息で行う検査で、喘息の状態の指標になるものとして、呼吸機能検査のピークフローとスパイロメトリーがあります。
ピークフローとは思い切り息を吐き出した時の息の速さをピークフローメーターという機器で測定します。
気管支喘息では気管支が炎症により細くなるので、息を吐き出す速度は遅くなります。
数値自体は性別、年齢、体格によって違うため、ピークフロー値の標準値か発作がない時の自己最良値を基準として、何%かを計測します。
基本的には80%以上が正常ですが、喘息発作時には80%以下に低下し、大きい発作では60%以下に下がってしまいます。
ピークフローの測定機器は小さく、家庭用のものもあり、自宅でも計測可能で、喘息発作の日々の指標にすることもできます。
スパイロメトリーは病院で測定する詳細な肺機能検査です。
- 1回の呼吸でできる換気(1回換気量)
- 思い切り息をしたときの換気量(努力肺活量)
- 標準的な数値と比較した時の肺活量(%肺活量)
- 努力肺活量のうち1秒間で吐き出した息の量(1秒量)
気管支喘息の場合には、息を吐くスピードが遅くなり1秒量が少なくなります。
呼気中の一酸化窒素濃度も喘息の指標になります。
一酸化窒素は血管拡張作用のある神経伝達物質で、通常でも息を吐くと、一定の割合で一酸化窒素が含まれています。
気管支喘息では、一酸化窒素の濃度が上昇することが知られており、その濃度を測定することで現在の喘息でおこる気道炎症の指標となります。
関連記事:気管支炎におすすめの市販薬9選!ランキング形式で紹介
小児気管支喘息は大人になると完治するの?
小児気管支喘息のうち、気管支が細く痰が多いことでおこるゼイゼイヒュウヒュウ(喘鳴)は成長とともに改善することが多いとされています。
ただしアレルギー性の気管支喘息の場合には適切な治療を行わないと、大人になっても治癒せずに喘息発作を繰り返してしまうこともあります。
また、アトピー性皮膚炎を合併している場合には、皮膚炎の治療程度も気管支喘息が治癒するかどうかに関与していることがわかっています。
気管支喘息やアトピー性皮膚炎の症状がある場合には、小児期の早い段階から適切な治療を行うことが重要です。
横浜内科・在宅クリニックでの対応
横浜内科・在宅クリニックでは、小児気管支喘息の診断と治療が可能です。
小さなお子様の場合、自身で不調を訴えることが難しい場合があるため、普段と様子が違う、息苦しそう、「ゼイゼイ」という呼吸があるなどお困りの症状があればお気軽にご相談ください。
発作を予防する生活習慣の工夫に関するアドバイスもおこなっています。
まとめ
小児気管支喘息について解説しました。
季節の変わり目、感染症の流行期にはゼイゼイヒュウヒュウするお子さんが増え、親御さんとしては心配な時期です。
気管支喘息の治療は発作時以外にも、喘息の程度によっては発作のない時からの治療やご自宅の環境整備も大切なポイントです。
記事を読んでいただき、治療を行いたい場合や思い当たる症状がある場合には病院へご相談ください。
参考文献
・日本小児アレルギー学会.小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2020.
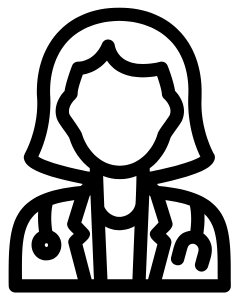
救急科専門医 Dr.新井 久美子

横浜内科・在宅クリニック 理事長:朝岡 龍博 医師
『クリニックに関わる全ての人を幸せに』
『最後まで患者様と病気と向き合います』
【経歴】
・2016年 名古屋市立大学卒業、豊橋市民病院 初期研修医勤務
・2018年 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科
・2020年 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科
・2021年 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科
・2022年 西春内科・在宅クリニック 副院長
・2023年 横浜内科・在宅クリニック 院長
・2025年 医療法人 幸龍家 理事長
【資格】
・舌下免疫療法講習会修了
・厚生労働省 指定オンライン診療研修修了
・緩和ケア研修会修了
・難病指定医
・麻薬施用者