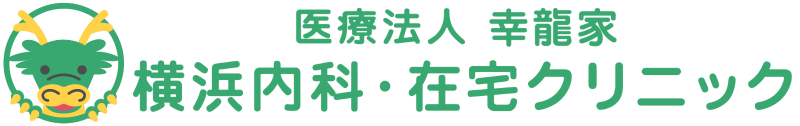小児てんかんの発作が出た時の正しい対応|原因や種類、緊急性の高い場合についても解説
てんかんとは、脳の細胞から異常な刺激対して何かしらのからだに症状が出ることを繰り返してしまう、脳の病気です。
私たちは手足を動かす時には、大脳が手足を動かすように電気刺激を出して、筋肉が収縮し、その通りに動かすことができます。
てんかん発作の場合には、病的な刺激のために、動かしたくないのに手足がぴくぴく動いたり、しびれたり、意識もぼんやりしたりしてしまうこともあります。
脳のどの部位に電気刺激が起こるかによっても症状がさまざまです。
てんかんは子どもから大人まで広い年代でかかる病気です。
特に、乳幼児から思春期(18歳くらい)にかけておこるものを小児てんかんとまとめています。
今回は小児てんかんの原因や症状、発作が出たときの対応方法について詳しく解説していきましょう。
小児てんかんの原因
小児てんかんの原因を以下3つに分類して解説していきます。
- 原因がはっきりしない特発性てんかん
- 脳になんらかのダメージがあることで起こる症候性てんかん
- 特殊な遺伝子異常でおこるてんかん
小児てんかん全体でみると、原因不明の特発性てんかんが多く、発症は生後から3歳までが多いとされています。
| 種類 | 特徴 |
| 特発性てんかん | 成長とともに発作頻度が減っていき、大人になるまでに治ってしまうこともあります。 |
| 症候性てんかん | 1歳までに発症することが多く、お母さんのお腹にいる間や生まれてくる時になんらかの原因で大脳の一部が傷ついて、それが原因になることがあります。 また、生まれつき脳の奇形や代謝異常、生まれた後に起こった髄膜炎や脳炎、外傷などによる脳損傷が原因になることもあります。 |
特殊な遺伝子異常で起こる小児てんかん | 最近研究が進んで原因となる遺伝子が特定されつつあります。 現在原因遺伝子がわかっているてんかんとしては、常染色体優性夜間前頭葉てんかん、家族性側頭葉てんかん、太田原症候群、Dravet症候群などがあります。 |
関連記事:熱性けいれんはどう対応すればいい?原因や後遺症を徹底解説
小児てんかんの発作の種類
小児てんかんの分類には先ほど説明した原因による分類(特発性、症候性)と、発作の出かたで分ける分類があります。
部分発作は脳の一部分から異常な電気刺激が発生して発作が始まるてんかんのことです。
全般性発作は、脳全体が一気に異常な電気刺激の発火があり、てんかん発作が起こります。
全般性発作の症状は多様です。
主に全般性強直間代(ぜんぱんせいきょうちょくかんだい)発作という全身がガクガク震えて意識もなくなるという発作を指します。
この強直間代発作で「てんかん」のイメージを持っている方が多いかもしれません。
小児てんかん全体でみると、部分てんかんが60-70%、全般てんかんが20-30%程度の割合になっています。
特発性の部分発作には中心・側頭部に棘波(きょくは)(*1)をもつ良性小児てんかん(良性ローランドてんかん)と、良性後頭葉てんかんがあります。
中心・側頭部に棘波(*1)をもつ良性小児てんかんという長い名前のてんかんは、生後18ヶ月から13歳くらいまでに発症します。
寝る直前に顔の片側が痙攣したり、よだれを垂らすような発作が特徴的です。
良性の名前の通り、発作の時間も短く、思春期までには発作がなくなるとされています。
良性後頭葉てんかんは小学生高学年くらいの学年に起こることが多く、以下の発作などがあります。
- 急に目の前が真っ暗になる
- 逆に眩しくなったりなどの目の症状がでる
目の症状しかでないので、てんかんの診断がつくのに時間がかかることがあります。
特発性全般てんかんにもいくつか種類があり、中でも子どもに多いものとして、小児欠伸てんかんと若年ミオクロニーてんかんがあります。
小児欠伸てんかんは、突然意識がぼーっとして話が途切れたり、動作が止まってしまいます。
食事中や授業中にぼーっとしたりします。
しかし、明らかにピクピクしたりするわけではないので、周囲の人に気づかれにくく単に「集中力がない」とされてしまうこともあります。
ミオクロニー発作は、電気が走ったかのように筋肉がビクっと収縮する発作です。
若年ミオクロニーてんかんは、ミオクロニー発作に全身のビクビクする強直間代性発作(きょうちょくかんだいせいほっさ)が一緒に起こります。
原因のある症候性の全般てんかんは、生まれてすぐから1歳までに発症することが多くあります。
全身や手足、頭部などがビクビクと痙攣する発作が特徴的です。
発作頻度も多く、治療にも関わらず症状が治らない難治性で、多くは精神遅滞や体の発達の遅れなども伴います。
症候性全般てんかんには、以下などが含まれます。
- ウエスト症候群
- レノックス・ガストー症候群
- ミオクロニー脱力発作てんかん
- ミオクロニー欠伸てんかん
| 棘波(きょくは)(*1)=持続時間が20~70msec(ミリセカンド)の尖ったてんかん発作の波形 |
小児てんかんと間違えやすいケース
特に多いのは、部分発作や欠伸発作のぼーっとするもので、精神疾患や発達の遅れとして誤って診断されてしまうことがあります。
熱性けいれんもてんかんと間違いやすい病気です。
熱性けいれんは感染症などで体温が急激に上昇した時に全身性のけいれんを起こす病気で、子供の5-8%でおこるとされています。
てんかんは繰り返す病気ですが、熱性けいれんは1度発作が起こっても半分は再発しません。
また、熱性けいれんは発熱後におこりますが、てんかんは発熱後以外でも発作が起こるのが大きな違いです。
赤ちゃんが大泣きした後に息を吐いた状態で呼吸が停まって、顔色が悪くなり意識を失う、脱力する、けいれんを起こすものに泣き入りひきつけ(憤怒けいれん)があります。
こちらも小児てんかんと分けて考える必要があります。
てんかんと違い「大泣き」や「びっくりする」などの動作とセットで起こるのが特徴です。
成長とともに発作頻度は減って自然に消失します。
チックは顔や首、肩などに突然起こるピクっとした動きを繰り返す病気です。
寝ている間は起こらず、緊張した場面などで出やすくなります。
てんかんと違い脳の活動異常で起こっているわけではないので、脳波検査をするとチックでは異常は認めません。
小学生などに多い、朝礼の時にしばらく立っていると意識を失って倒れて全身を硬直させる発作が起こることがあります。
これは起立性調節障害という自立神経失調の症状です。
トイレで排尿、排便後などに意識を失う迷走神経反射も自立神経失調の症状です。
てんかんと違い、多くは意識を失うきっかけがはっきりしています。
小児てんかんと間違えやすい病気は症状のみでは判断がつきにくいこともあります。
発作が起こった状況などを詳しく聞くことで正確な診断につながります。
発作が出た時にできる親の対応・緊急性の高い場合は?
発作が出たときのポイントは以下の3つです。
- 安全な場所に移動させる
- 息がしやすいように服を緩め横を向かせる
- 5分前後しても発作が自然に改善しない時は救急車を呼ぶ
お子さんのてんかん発作が起こると、普通は焦ってしまいますよね。
やるべきことが事前にわかっていれば、少し落ち着いて行動できそうですよね。
少し詳しく解説しましょう。
1. 安全な場所に移動させること
ぼーっとしたり、手足がビクビク動いていたりする場合、倒れたり周りのものにぶつかってしまい、それが原因で怪我をしてしまうことがあります。
まずは、焦らずひと呼吸して落ち着いて、お子さんを安全な場所に移動させましょう。
特に屋外の道路などで起こってしまった場合には、事故につながる可能性もあります。
屋外での発作時は安全な場所に移動するのは、非常に重要なポイントです。
2. 息がしやすいように服を緩め、嘔吐などをしても大丈夫なように横を向かせましょう
てんかん発作が起こっても、息がしっかりできていれば緊急の問題はありません。
首もとの詰まった服などは息がしにくくなることもあるので、できればボタンなどを外して緩めましょう。
服を脱がせる必要はありません。
意識を失って吐いてしまうこともあります。
上を向いていると吐いたものが口に溜まって誤って吸い込んでしまうことがあります。
そうならないように、余裕があれば、横を向かせましょう。
横を向くと、気道も広がって息もしやすくなります。
よく、てんかん発作時に息ができるように口をこじ開けてハンカチ、タオル、はしやスプーンなどを噛ませると思っている方がいますが、こちらはしてはいけません。
口に異物を入れると余計危険になってしまいます。
息が止まってしまっている、首もとを緩めても息苦しさが改善せず顔色が悪くなっている場合は緊急性が高いため、すぐに救急車を呼びましょう。
3. 5分以上てんかん発作が持続する場合には、救急車を呼ぶ
てんかん発作の持続時間を知ることは大切です。
時計などが手元にあれば、発作が起こった時間を確認しておきましょう。
数分以内に自然に発作が治って意識が戻れば、落ち着いてから病院を受診しましょう。
経過をみても治らない場合は、救急車を呼びましょう。
5分経たないと救急車を呼べない訳ではありません。
目の前でお子さんのてんかん発作が起こっての5分間は、非常に長く感じられると思います。
以下などの場合は5分待たずに救急車を呼んでください。
- 安全な場所に移して横を向けたりしても、発作がおさまらない場合
- 何度も発作が起きている場合
- 息をしていない場合
小児てんかんの検査と治療について
小児てんかん検査では以下の検査を行います。
検査 | 内容 |
血液検査 | 症候性てんかんの原因となる代謝異常で低血糖の有無などを行います。 |
| 心電図 | 不整脈などの有無を確認します。 |
| 頭部画像検査(CT、MRIなど) | 症候性てんかんの原因になるようや脳の異常所見がないかを確認します。 |
脳波検査 | 脳の異常な電気刺激を検出することができます。 発作の時の脳波で異常があればてんかんの診断と、どのようなタイプのてんかん発作かを診断することができます。(脳波に異常がでないタイプのてんかんもあります) |
関連記事:子供がお腹を痛がるときはどうすればいい?考えられる腹痛の原因や危険なサインとは?
小児てんかんは完治するのか?
完治するかどうかは、てんかん発作のタイプによります。
中心・側頭部に棘波をもつ良性小児てんかんや小児欠伸てんかんは、治療薬である抗てんかん薬がよく効きます。
成長とともに発作の回数も減って、多くの場合で最終的には抗てんかん薬をやめることが可能です。
若年性ミオクロニーてんかんは抗てんかん薬で発作を抑えることが可能です。
投薬をやめてしまうと再発することが多くあります。
基本的には長期間抗てんかん薬を継続して飲む必要があります。
難治性てんかんといわれる症候性全般てんかん(ウエスト症候群、レノックス・ガストー症候群など)は、抗てんかん薬を使用しても発作を抑えることができないことがあります。
最近では新しい抗てんかん薬も出てきており、さらなる治療の進歩に期待がかかりますね。
また難治性の場合には、食事療法(ケトン食療法)やてんかん外科手術などを組み合わせて行うこともあります。
小児てんかんに使える医療制度
小児てんかんの中でも難治性てんかんに分類される以下のものは、小児慢性特定疾病医療費助成を使って外来と入院の医療費の自己負担が原則2割にすることができます。
- West症候群
- 結節性硬化症
- レノックス・ガストー症候群
- 乳児重症ミオクロニーてんかん
また、1歳未満の乳幼児の場合には、お住まいの市町村にもよりますが、乳幼児の医療費の自己負担全額もしくは一部が助成されます。
発達の問題があり、重度の障害があると病院で認定を受けた場合には、重度心身障害児医療費助成で、医療費の自己負担の全額もしくは一部も助成されます。
てんかんの原因が指定難病(太田原症候群、限局性皮質異形成、内側側頭葉てんかん、スタージ・ウェーバー症候群など)の場合には、外来と入院の医療費の自己負担が原則として2割になる難病医療費助成を受けることができます。
日常生活での注意点
てんかん発作の20%は特定の刺激や出来事がきっかけで起こると言われています。
多くは以下などが刺激となり発作が起きます。
- 緊張
- ストレス
- 睡眠不足
- 発熱
避けられないものもありますが、睡眠不足などは生活習慣を整えることで予防が可能です。
実はお風呂に入ることも、てんかん発作を誘発する因子であると言われています。
お風呂は滑りやすかったり、溺れるなどのリスクがあるため以下の事などに注意が必要です。
- 必ず誰かと一緒に入る
- 何かあったときにすぐ救出できるように鍵をかけない
- 転倒しても危なくないようにマットを引く
- 湯船にはつからずにシャワーだけにする
いざ、湯船の中でてんかん発作が起こってしまった場合には、お風呂の水を抜きましょう。
溺れてしまうことを防ぐことができます。
てんかん発作が光の刺激で誘発されることもあります。
以前、あるアニメーションをみていた全国の子どもたちがテレビのピカピカっと光る映像を見た後にてんかん発作を起こしたということで話題になりました。
その際、暗い部屋かつ近い距離でテレビをみていた子どもたちに、よりてんかん発作が起こりやすかったということが調査でわかりました。
テレビを見る時には部屋を明るくして、適切な距離をとって楽しみましょう。
すでにてんかん発作がテレビなどの光刺激で起こることがわかっている場合には、できるだけ刺激を避けるようにするのが望ましいでしょう。
小児てんかんがあるからといって、特別に運動などを避ける必要はありません。
てんかん発作が起こってもすぐ対処できるように、家族、教育施設(保育園や学校など)、主治医の先生や医療スタッフで情報を共有し、安全な環境作りをしておけば安心です。
スポーツでも登山やスキー、流れの早い川や海などは危険な場所ですので、できれば避けることをおすすめします。
関連記事:子供がインフルエンザになった時の親の対応|風邪や似ている病気との違いについても解説
横浜内科・在宅クリニックでの対応
てんかんは、突然ぼーっとしたりする欠伸発作や顔だけ、腕だけの部分発作は見逃されてしまうことがあります。
この記事を読んで「てんかんかも?」と思い当たることがあれば、お近くの病院または横浜内科・在宅クリニックへご相談ください。
まずは正しい診断をつけることから始まります。
てんかん発作のタイプによっては、小児てんかんの専門病院での検査・治療が必要な場合もあります。
てんかんの治療はてんかん発作のタイプに合わせて抗てんかん薬を使います。
治療を始めた後は、薬で発作が抑えられているか、薬の副作用がでていないか、薬の飲み忘れがないかなどを定期的な外来診察で確認していきます。
1種類の薬で発作が抑えられない場合には、抗てんかん薬を変更したり、種類の違う抗てんかん薬を追加して治療を行うこともあります。
てんかん発作が起こった場合、5分以上発作が続いたりその他心配な症状があれば、救急の受診が必要です。
まとめ
今回は、小児てんかんの原因や症状、発作が出たときの対応方法について解説しました。
一言で小児てんかんといっても、症状や原因となる病気もさまざまです。
一部の小児てんかんは成長とともに自然に出にくくなり、完治します。
また、てんかんと区別すべき病気についても解説しました。
記事を読んで思い当たる症状やご不安があれば、ぜひご相談ください。
参考文献