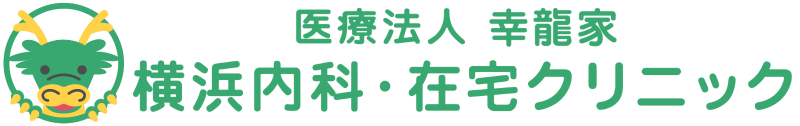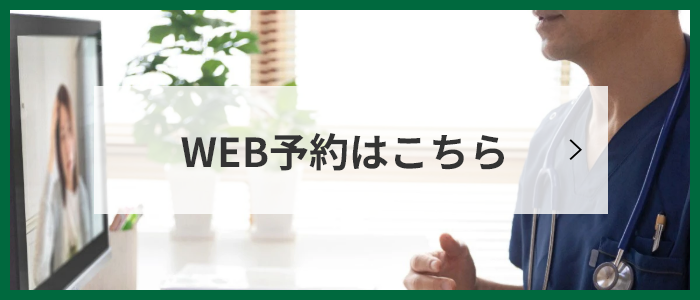川崎病とは?動脈瘤や心筋梗塞を引き起こす疾患
皆さんは、「川崎病」という病気をご存じでしょうか。
小さい子どもに多く見られる病気であるため、お子様をお持ちの方なら耳にしたことのある方もいらっしゃるかと思います。
今回は、時として命にも関わる病気「川崎病」について原因や症状、治療法などを解説していきます。
川崎病とは
川崎病は、小児科医である川崎富作という医師が最初に報告したことからその名がつけられた原因不明の病気です。
4歳以下の子どもに多く見られ、全身の血管に炎症が起こる事です。
以下の6つの主要な症状が現れます。
| 症状 | 特徴 |
| 高熱 | 38℃以上の高熱が5日間以上続く |
| 目の充血 | 両目の白目部分(眼球結膜)が赤く充血 |
| 真っ赤な唇とイチゴのようなブツブツの舌 | 唇が赤くなったり、乾いてひび割れる 舌はイチゴ状に赤くブツブツが出る |
| 不定形発疹 | 蕁麻疹のような発疹が現れる BCG接種した部位が赤く腫れることがある |
| 手足のしびれ | 手のひらと足の裏が紫がかった赤色に貼れることがある 熱が下がる頃、指先から皮むけが始まる |
| 首のリンパ節の腫れ | リンパ節が赤く腫れる 膿むことはしない |
上記の他、関節痛や下痢、腹痛などの症状が現れることがあります。
定型川崎病
川崎病の特徴的な6つの症状のうち、以下の場合に定型川崎病と診断されます。
- 5つの症状が見られた場合
- 4つの症状と冠動脈瘤※が見られる場合
※冠動脈瘤:心臓に血液を送る血管の冠動脈の壁が炎症で弱くなり、血圧に耐え切れずにコブのように膨らんだ状態
不全型川崎病
主要症状のうち5つ以上揃わないが、他の病気では説明できず、冠動脈に異常がみられる場合に不全型川崎病と診断されます。
現れる症状が少ないため風邪などの他の病気と間違えられることで診断が遅れることもあります。
関連記事:溶連菌の潜伏期間は?感染したら出席停止?
川崎病の原因
川崎病の原因は未だに不明なままですが、昔からさまざまな説が論じられてきました。
カビ、細菌、ウイルスなどの病原微生物の体内への侵入が、過剰な免疫反応の引き金となり、起こっているのではないかと考えられています。
また、ヨーロッパ諸国に比べて日本人が約10~20倍多く発症していることから、遺伝的な要因もあるのではないかという考え方もあります。
関連記事:蕁麻疹の対処法は?全身が痒くて夜寝られないときはどうする?
川崎病の後遺症
血管炎
血管炎とは、その名の通り何らかの影響で血管が炎症を起こしている状態のことを指し、虚血、壊死、臓器の炎症を伴う場合があります。
冠動脈瘤
冠動脈瘤とは、冠動脈に炎症が起き、血管の壁が血圧に耐えられなくなることで、一部が膨らんで瘤のようになる症状です。
大動脈から冠動脈に枝分かれする部分に瘤ができやすいです。
心筋梗塞
心筋梗塞とは、冠動脈の一部が完全に塞がることで、その先の器官が機能しなくなる状態を言います。
冠動脈瘤ができると、血流が悪くなるため血栓ができやすくなります。
川崎病はうつる?
川崎病の原因は分かっていません。
男児が女児よりも1.3倍程度多く発病していたり、地域的な流行がみられたりすることがありますが、現在は人から人へ感染する病気とか考えられていません。
関連記事:アデノウイルスの症状とは?潜伏期間や感染経路について解説
川崎病の治療について
免疫グロブリン療法
免疫グロブリン療法という全身の炎症を抑える薬を静脈内に点滴することで、冠動脈瘤ができるのを防ぎます。
約1日かけて点滴で注入します。
80~90%の患者さんは1回の投与で熱が下がりますが、2回目の投与が必要な患者さんもいます。
アスピリン療法
アスピリンという血管の炎症を抑えたり、熱を下げたり、血液を固まりにくくする薬を内服する治療法です。
こちらも、冠動脈瘤ができるのを防ぐ効果があります。
約2~3か月服用を続け、免疫グロブリンとの併用により、数日以内に熱が下がり、ほかの症状も治まるので、冠動脈瘤も予防することができます。
副作用として出血時に血が止まりにくくなることがあります。
ステロイド療法
主に免疫グロブリンを投与しても、熱が下がらず、症状が改善しない患者さんへ、全身の炎症を抑える為に行います。
はじめは点滴から開始し徐々に内服治療へ移行します。
退院後の生活は、冠動脈に後遺症がなかった場合でも予防的に2〜3か月内服を続ける必要がありますが、日常生活で気をつけることは特にありません。
後遺症として冠動脈瘤が残った場合は、血を固まりにくくする治療がしばらく続きます。
その他の治療
上記の治療で症状が改善しない時は、好中球エラスターゼ阻害剤、シクロスポリンの投与、血漿交換といった処置を行うこともあります。
横浜内科・在宅クリニックでの対応
川崎病が疑われる場合、当院では近隣の専門医療機関への紹介を行っています。
症状が少ない場合、他の病気と間違いやすい病気ですが、丁寧な問診と診察で患者様が適切な治療を受けられるように診療を行っています。
お困りの症状があればお気軽にご相談ください。
まとめ
かつて、川崎病はかかってしまうと亡くなってしまう恐ろしい病気でした。
しかし、現在は治療法が確立されていること、冠動脈瘤の早期発見ができることで亡くなるリスクが大幅に下がっています。
特に、原因不明の熱が続く場合には、熱以外に川崎病に特徴的な症状がないか十分に気をつけ、普段のお子さんの様子と様子が違うと感じた場合は小児専門の医療機関を受診するようにしましょう。
参考文献

横浜内科・在宅クリニック 理事長:朝岡 龍博 医師
『クリニックに関わる全ての人を幸せに』
『最後まで患者様と病気と向き合います』
【経歴】
・2016年 名古屋市立大学卒業、豊橋市民病院 初期研修医勤務
・2018年 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科
・2020年 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科
・2021年 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科
・2022年 西春内科・在宅クリニック 副院長
・2023年 横浜内科・在宅クリニック 院長
・2025年 医療法人 幸龍家 理事長
【資格】
・舌下免疫療法講習会修了
・厚生労働省 指定オンライン診療研修修了
・緩和ケア研修会修了
・難病指定医
・麻薬施用者