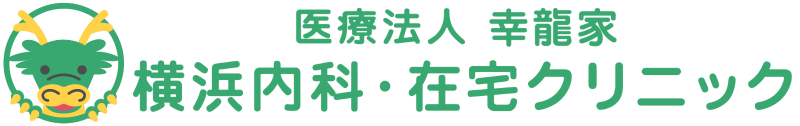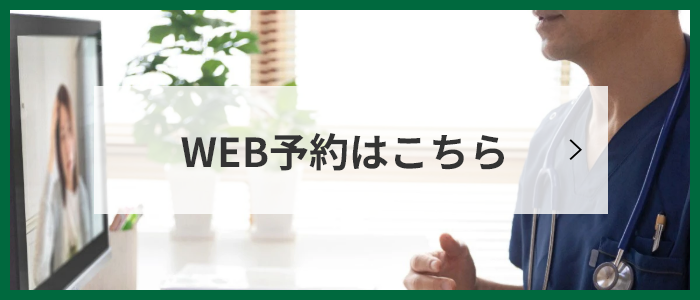カンピロバクター感染症とは|潜伏期間や症状について解説
カンピロバクター感染症とは、日ごろ一般家庭の食卓に出てくる牛や豚、鶏などの食品から感染することが多い食中毒です。
本記事では、カンピロバクター感染症について症状や予防方法などについて詳しく解説します。
カンピロバクターとは?
カンピロバクターは食中毒発生件数の中で上位を占める食中毒菌です。
ほかの菌に比べ少量であっても食中毒を引き起こし、5~7月の暖かい時期や10月前後の行楽シーズンに多く発生します。
7割が飲食店で発生しており、家庭や学校などでも発生することがあるため注意が必要です。
カンピロバクターの症状
カンピロバクター感染症の主な症状として以下などがあげられます。
- 下痢(しばしば血便を伴う)
- 腹痛と腹部のけいれん
- 発熱(38℃以下が多い)
- 吐き気
- 嘔吐
- 倦怠感
- 頭痛
初めに発熱し、遅れて下痢症状がでるといったケースや発熱はなく下痢症状のみのケースなど症状は人によって異なります。
多くの場合、1週間程度で症状が改善していき、命にかかわるようなことは稀です。
しかし、小さなお子様や高齢者、免疫力が下がっている人は重症化することもあるため注意が必要です。
カンピロバクターに感染してから数週間後にギランバレー症候群を合併することがあります。
日本国内での発症率は10万人に1~2人ほどです。
カンピロバクター感染後、数週間して手足のしびれや脱力感があり、徐々に力が入らなくなりますが、一般的に4週前後で症状のピークを迎え徐々に回復に向かいます。
カンピロバクターの潜伏期間は?
カンピロバクターの潜伏期間はおよそ2~10日程度と他の食中毒菌とくらべ長いことが特徴です。
潜伏期間が長いため症状が出たときには、原因となった食べ物がわからないといったこともあります。
関連記事:腹痛が起こる・続く原因のまとめ|緊急性の高い痛みの特徴も解説
カンピロバクターの感染経路と予防策
主な感染経路
カンピロバクターは主に食肉、とりわけ鶏肉を通じて感染します。
特に注意が必要なのは、生や加熱不足の鶏肉です。
焼き鳥や鶏のたたきなどで生焼け状態の鶏肉を食べることで感染するケースが最も多く見られます。
もう一つ気を付けたいのが、調理中の思わぬ観戦です。
生肉を切ったまな板や包丁を使用してそのまま野菜などを切ったり、生肉を触った手で調味料の容器を触るなどで細菌が思わぬところに広がってしまうことがあります。
有効な予防法
予防の基本は、適切な加熱と清潔な調理環境です。
鶏肉は中心部の温度が75度以上で、1分以上加熱する。
一般家庭で調理するときは、肉汁が完全に透明になり、ピンク色の部分が残っていない状態まで火を通すようにしましょう。
また、調理機器の扱いにも注意が必要です。
生肉用のまな板と包丁は、他の食材用と分けて使用するようにしましょう。
生肉を切ったまな板と包丁は使用後にすぐ集めのお湯と洗剤でしっかりと洗い、よく乾燥しておきます。
まな板は定期的に熱湯をかけて消毒するとより安全です。
最後に忘れていけないのが手洗いです。
生肉を触った後は必ず石鹸を使用し、指の間や爪なども丁寧に洗います。
30秒程度かけてしっかり洗うことで、手についた細菌をほぼ完全い除去することができます。
カンピロバクターはうつる?
カンピロバクターは乾燥に弱く、空気中に長く生存することができないため、人から人へ感染することはほとんどありません。
ただし、感染者の便や嘔吐物を介して感染することがあるため、看病する場合、便や嘔吐物に直接触れないように手袋を着用するようにしてください。
カンピロバクターに感染したときの治療
カンピロバクターに感染した場合、特別な治療を必要としないケースが多いですが、下痢と発熱による脱水に注意が必要です。
経口補水液やスポーツドリンクなどでこまめな水分補給を行うことで脱水を予防します。
症状が安定するまでは食事を控えめにし、消化の良いおかゆなどを中心に過ごしましょう。
病院で受けられる治療
脱水が強い、口から水分が取れない場合、点滴を行います。
症状が重い場合、抗生物質の処方が必要になることもあります。
下痢止めは、菌の排出を遅らせるため、基本的に使用しません。
関連記事:腹痛と下痢が続く原因|コロナの可能性は?治し方や病院での対処法を解説
カンピロバクターは治るまで何日かかる?
カンピロバクター感染症は、食事療法、対処療法を行い、およそ1週間程度でほとんどの方は症状が改善します。
細菌が排出されるのを待つことが重要で、すぐに治す方法はありません。
カンピロバクター感染時に処方される薬は?
症状が強い場合は、消化を助けるお薬や腸内環境を回復させるため整腸剤が処方されます。
高熱や出血を伴う下痢がある場合は、アジスロマイシンなどの抗生物質が処方されることもあります。
横浜内科・在宅クリニックでの対応
カンピロバクター感染症は、特効薬がありません。
当院では、問診と診察で患者様の状態をしっかりと診させていただき、症状に合わせた薬の処方や脱水が認められる場合の点滴処置が可能です。
基本的にご自宅で安静にしていただくことで症状が快方に向かいますが、ご自宅での過ごし方に関するアドバイスも行えます。
お困りの症状やどうしたらいいかな?といった疑問点などあればお気軽にご相談ください。
【まとめ】カンピロバクターは日頃からの衛生管理で対策しよう
カンピロバクターによる食中毒は、十分な加熱と二次汚染の防止や消毒を徹底することで防ぐことができます。
お肉を調理するときは、調理や調理器具の扱いに注意して食中毒を防ぎましょう。
普段から手洗い・うがいをしっかり行うことで衛生面も気を付けることが大切です。
参考文献
- NIID 国立感染症研究所 カンピロバクター感染症とは
- 厚生労働省検疫所FORTH カンピロバクター感染症
- 健栄製薬カンピロバクター感染症
- 病気スコープ カンピロバクター食中毒は人からうつる?予防法や潜伏期間について
- EPARKくすりの窓口コラム カンピロバクター食中毒の基礎知識と治療に用いられるお薬

横浜内科・在宅クリニック 理事長:朝岡 龍博 医師
『クリニックに関わる全ての人を幸せに』
『最後まで患者様と病気と向き合います』
【経歴】
・2016年 名古屋市立大学卒業、豊橋市民病院 初期研修医勤務
・2018年 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科
・2020年 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科
・2021年 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科
・2022年 西春内科・在宅クリニック 副院長
・2023年 横浜内科・在宅クリニック 院長
・2025年 医療法人 幸龍家 理事長
【資格】
・舌下免疫療法講習会修了
・厚生労働省 指定オンライン診療研修修了
・緩和ケア研修会修了
・難病指定医
・麻薬施用者