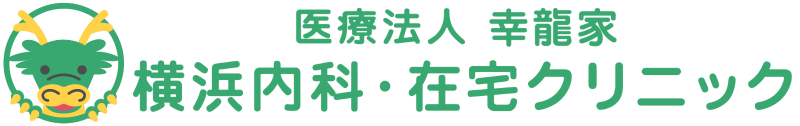【緊急性の高い食物アレルギー】アナフィラキシーショックの対応法
アナフィラキシーショックとは、アナフィラキシーに血圧低下や意識障害を伴うもののことです。
アナフィラキシーとは、アレルゲン(*1)にさらされる(暴露される)ことにより全身性にアレルギー症状が引き起こされ、生命の危機にもなる過敏なアレルギー反応のことです。
アナフィラキシーは、アレルゲンが体内に入ってから数分~数時間で症状が出現します。
適切な治療がされなければ気道のむくみ(浮腫)による窒息や重度の血圧低下によって、重い後遺症を残したり死亡したりすることもあります。
時に発症から数分で呼吸不全や心肺停止となることもある病気です。
病院到着前の対応(エピペンを使用する、回復体位で休ませるなど)が非常に重要となります。
アナフィラキシー、特にアナフィラキシーショックとなっている人に遭遇した場合は、医療関係者でなくとも適切な対応ができることが望まれます。
今回は、アナフィラキシーショックの原因や、症状、対処法などについて詳しく解説していきます。
| アレルゲン(*1)=食べ物や医薬品、昆虫の毒などアレルギーを引き起こす原因物質 |
アナフィラキシーショックが起こる原因
アナフィラキシーショックは特殊な病気(マスト細胞症)を除き、アレルゲンに暴露されることで発症します。
アレルゲンとしては、乳製品や鶏卵、小麦などの食物が代表的ですが、以下なども原因となります。
- 抗生物質などの医薬品
- ハチなどの昆虫毒
- 医療用手袋などに使われる天然ゴム
普段はアレルギー症状がでないものでも、運動や情動的ストレス(興奮など)が加わることでアナフィラキシーを引き起こすことがあります。
また、非日常的な活動を行った時や月経前や感染症で体調がすぐれない時にもアナフィラキシーが出現・悪化しやすくなるため注意が必要です。
アナフィラキシーの予防で最も重要なことはアレルゲンを避けることです。
どのようなものがアレルギーの原因となるかを知っておくことは大変重要になります。
アレルギー反応を起こす頻度の多い食物・医薬品・昆虫毒に関して、さらに詳しく説明いたします。
アナフィラキシーの原因の約7割が食物に関連したものです。
文部科学省の統計では、小学生~高校生の約4.5%が何かしらの食物アレルギーを持っており、食物アレルギーを持つ子供の9人に1人がアナフィラキシーを経験したことがあるとされています。
アナフィラキシーショックに至った原因として多いものは以下などがあります。
・鶏卵(23.9%)
・牛乳・乳製品(22.5%)
・小麦(16.6%)
・木の実類(12.8%)
・落花生(7.3%)
・甲殻類(エビ・カニなど)(3.6%)
・果物類(2.9%)
・そば(2.7%)
・魚卵(イクラ・たらこなど)(2.3%)
年齢別でみると、0~3歳は鶏卵、4~6歳は牛乳・乳製品、7~19歳は落花生、20歳以上は小麦が原因として最も多いです。
幼児では離乳食を進めていく段階でアレルゲンに暴露することがあります。
また、小児期には食後に激しい運動をしたり、感染症に罹患したりすることが多くなります。
集団生活の中で情動的ストレスも増え、普段はアレルギー症状がでない食物でもアレルギー症状が出現したりアナフィラキシーを起こしたりすることがあります。
どちらも注意が必要です。
アナフィラキシーの原因の1割強は医薬品に関連したものです。
原因として多いのは、以下のようなものです。
・造影剤などの診断用薬(20.3%)
・輸血製剤・ワクチン・血清などの生物学的製剤(20.1%)
・抗腫瘍薬(12.7%)
・抗生物質(12.4%)
原因として最も多いのは造影剤などの診断用薬ですが、薬剤の使用頻度が高いことが主な要因です。
造影剤によるアナフィラキシー発症率は0.1%程度と言われています。
気管支喘息などアレルギー性の疾患のある人では、薬剤によるアレルギーも発症・重篤化しやすいです。
そのような病気をお持ちの場合は、造影検査を受ける際や薬の処方を受ける際に医師にご相談ください。
関連記事:アナフィラキシーって?コロナのワクチン接種でもなるの?│症状・治療・原因・対応
昆虫毒はアナフィラキシーの原因の5%弱で、その多くがハチ毒によるものです。
人口の0.36%はハチ毒に過敏症を持っているといわれています。
短期間の間に2回の暴露があるとアナフィラキシーを生じやすいとされています。
林業や木材製造業の従事者、農業従事者など職場で蜂に刺されるリスクの高い人は発症しやすいです。
ハチの中ではスズメバチが有名です。
しかし、ハチを原因としたアナフィラキシーではアシナガバチによるものが最も多くなっています。
ミツバチでも発症することがあるため、スズメバチではないから大丈夫などと油断しないようにしましょう。
関連記事:小児てんかんの発作が出た時の正しい対応|原因や種類、緊急性の高い場合についても解説
アナフィラキシーショックの発症時間
アナフィラキシーは、アレルギー症状が出現してから数分でアナフィラキシーショックとなり死に至ることがあります。
発症初期の時点では進行の速さや最終的な重症度の予測は困難です。
アレルゲンへの暴露からアナフィラキシーショックに至るまでの時間(中央値)は、薬物では5分、ハチでは15分、食物では30分であったとの報告があります。
心肺停止に至った場合は、蘇生に成功した場合でも低酸素脳症などにより重篤な後遺症を残すことがあります。
そのため、アナフィラキシーを疑った場合は迅速な対応が必要となります。
また、アナフィラキシーでは治療後に遅れて再度症状が出現すること(二相性反応)や数時間以上経過してから症状が出てくること(遅延反応)があります。
多くはアレルゲンに暴露してから4時間以内に症状が出現します。
しかし、アレルゲンに暴露してから4時間後以降であっても重篤な症状が出現したという報告もあるため、アレルゲンの暴露から時間がたっていたとしても注意が必要です。
アナフィラキシーショックの症状
アナフィラキシーショックでは以下のような、様々な症状が出現します。
それでは、各症状について解説していきます。
皮膚症状は80~90%にみられる症状です。
かゆみを伴うじんましんが有名です。
じんましんに限らず、以下など様々な形で出現することがあるため、注意が必要です。
・紅斑(皮膚が赤くなる)
・粘膜疹(口腔内や結膜などの粘膜の異常)
・血管性浮腫(唇や舌などの局所的なむくみ)
・麻疹様皮疹(はしかのような小さいぷつぷつとした皮疹)
呼吸器症状は70%以下の割合でみられる症状です。
以下などの症状がよくみられます。
・鼻水や鼻づまり
・喉の違和感などの花粉症に似た症状
・息苦しさや咳など喘息に似た症状嗄声(かすれ声)や息切れ
また、気道の浮腫による喘鳴や呼吸停止などの重度の症状が出現することもあります。
関連記事:花粉で喉が痛い・咳が止まらない時の対処法|インフルエンザとの違いは?
呼吸器症状は45%以下の割合でみられる症状です。
アレルギー症状としてはあまり一般的でないため見過ごされがちです。
アナフィラキシーでは腹痛・下痢・嘔吐・食事の飲み込みにくさなどの症状が出現することがあります。
心血管系の症状は45%以下、中枢神経系の症状は15%以下の割合でみられる症状です。
心血管系として以下の症状などが出現します。
・動悸や息切れ
・頻脈や徐脈
・血圧低下
・意識障害
中枢神経系として以下の症状などが出現します。
・突然の不安感や絶望感
・ふわふわとしためまい
・興奮
皮膚症状や呼吸症状はアレルギー疾患で比較的よくみられる症状であり、アレルギー症状として認識されやすいです。
しかし、皮膚症状より先に消化器症状や心血管系・中枢神経系の症状が出現することもあるため注意が必要です。
関連記事:りんご病(伝染性紅斑)になったら病院へ行くべき?症状を解説|大人にもうつる?
アナフィラキシーショックの対応法
アレルゲンに暴露した場合には、症状の有無や程度、進行速度などを注意深く経過観察することが必要です。
無症状もしくは症状が局所的な皮膚症状や喉の違和感のみで、急速な悪化(数分~数時間での症状の悪化)がない場合は運動を避けて安静にしつつ、対症療法などで経過観察をしていただくことが可能です。
その際は症状が急激に悪化する可能性もあるため、一人で過ごすことは避けるようにしてください。
- 症状が軽くてもでもアレルゲンの暴露から短期間(数分~数時間)で発症・悪化した場合
- 皮膚症状に加えて呼吸器症状や消化器症状など複数臓器の症状が出現している場合
- 過去にアナフィラキシーを起こしたアレルゲンに暴露した場合
などは重症化するリスクがあるため、エピペン※1(アドレナリン自己注射薬)が手元にあれば使用を検討してください。
また、エピペンの使用の有無にかかわらず医療機関へ受診するようにしましょう。
- その他の症状があまりなくても、ひどい咳が出たり、動くと息切れがしたり、息苦しさを感じる場合
- 顔色が悪くなったり、立ちくらみがしたり、血圧が下がったりした場合
緊急での対応が必要です。
すぐに救急要請をして、エピペン※1があれば使用してください。
救急車を待つ間は横になって安静にすることが基本です。
・意識がしっかりしている場合
本人の楽な姿勢でよいですが、吐き気・嘔吐がある場合は吐物を誤嚥しないよう体を横向きにする。
血圧が低い場合は足を挙上するなどの対応がより望ましいです。
※1 エピペンは本人に処方されているもののみ使用可能です。
また、エピペンが使用できるのは本人・保護者・学校教職員・保育士・救急救命士・医師・看護師に限られます。
それ以外の方は使用することができませんのでご注意ください。
エピペンの使い方、アナフィラキシーショックの治療について
前項ではアナフィラキシーを疑う方を発見した時の対応について解説しました。
本項では病院到着前に使用すべきエピペンの使い方と医療機関でのアナフィラキシーの治療について説明します。
エピペンとは
エピペンはアナフィラキシーがあらわれた時に使用します。
病院での治療を受けるまでの間、症状を一時的に和らげてアナフィラキシーショックを予防するための補助治療剤(アドレナリン自己注射薬)です。
エピペンは過去にアナフィラキシーを発症し、エピペンを処方することが可能な医師の診察を受けて、必要と判断された場合に処方されます。
エピペンは本人だけでなく、保護者・学校教職員・保育士・救急救命士・医師・看護師も使用することができる補助治療剤です。
アナフィラキシーは児童での発症も少なくありません。
自身での使用が困難な場合もあるため、エピペンの処方を受けた方の保護者や学校職員、保育士などの医療関係者でない人も使えるようにしておく必要があります。
エピペンの使い方
- エピペン本体をケースから取り出し、青色の安全キャップを取り外します。
- 太ももの前外側にオレンジ色の先端部分を垂直に、「カチッ」と音がするまで強く押し付け、5秒以上押し付けて注射する(ズボンなどの衣服の上からでも注射可能です)。
- エピペンを太ももから抜き取る。この際にオレンジ色の先端部分が伸びていることを確認する
- 使用済みのエピペンをオレンジ色の先端部分を下にしてカバーにしまう(蓋は閉まりません)。
※エピペンの使い方を学ぶ際は「練習用エピペントレーナー」が有用です。
エピペンの処方を受ける際やエピペンの講習会を受講した際に指導や手技確認のために使用されます。


※図:エピペン公式サイト ガイドブックより引用
医療機関での治療
アナフィラキシーは、アレルゲンに対して免疫が過剰に反応することで複数臓器にアレルギー症状を起こすものです。
アレルゲンが体から除去されて免疫反応が正常化すれば症状は改善、消失します。
そのため、免疫反応が正常化するまで全身状態を維持することが最も重要な治療となります。
アナフィラキシーショックで特に致命的な影響を与えうる症状としては、気道の浮腫による窒息と血圧低下があります。
アナフィラキシーショックではこれらが特に注意が必要です。
治療においては気道の拡張と血圧上昇の効果が迅速に得られるアドレナリンの早期投与が重要となります。
気道が閉塞しかかっている、アドレナリンを使用しても気道の狭窄が進行する場合は、気管挿管を行うこともあります。
血圧低下に対しては点滴を行って血管の中の水分量を増やしたり、アドレナリン以外の昇圧薬を併用したりして血圧の維持を行います。
また、アレルギー症状の原因となるヒスタミンの作用を抑える薬剤(抗ヒスタミン薬)や免疫系の働きを抑制する薬剤(ステロイド)なども併用して治療を行います。
関連記事:【冬から注意】子供の水疱瘡(みずぼうそう)|症状や潜伏期間、予防接種について
アナフィラキシーショックの後遺症や再発について
アナフィラキシーショックは、迅速に治療を受け、症状が改善するまでに呼吸や血液循環の維持がされれば後遺症は残りません。
しかし、気道閉塞による窒息や高度の血圧低下、心静止に至ってしまった場合は、死亡したり以下のような重度の後遺症が残ることがあります。
- 低酸素脳症となって意識障害や前頭葉機能低下などの高次機能障害が残る
- 不随意運動が出現
アナフィラキシーショックはアレルゲンの特定とその除去で予防ができる病気です。
しかし、アレルゲンとなる食物には、小麦や牛乳など日常生活で頻用され様々な食品に含まれているものも多くあります。
そのため、注意をしていても間違って口にしてしまうなど、意図せずアレルゲンに暴露してしまうことがあり、アナフィラキシーを再発してしまうことは少なくありません。
そのため、アレルゲンに暴露をしてしまった際はアナフィラキシーショックにならないように迅速に対応することが重要です。
アナフィラキシーショックの予防法
アナフィラキシーショックの予防には、原因となったアレルゲンの特定とその除去が最も重要です。
アレルゲンとなる食物には、日常生活で頻用され多くの加工食品に含まれているものもあります。
そのため、加工食品などを食べる際は原材料名などを確認して、アレルゲンが含まれていないことを確認することが重要となります。
アレルゲンとなる食物のうち、特定原材料に指定されている7品目(卵、乳、小麦、えび、かに、落花生、そば)に関しては、容器包装された食品において表示義務があります。
わかりやすく表記されていることが多いためそれも参考にするとよいでしょう。
&nbp;
また、アナフィラキシーを悪化させる因子としては、以下などがあり、これらの状況を避けることも予防につながります。
- 運動や情動的ストレス
- 非日常的な活動
- 月経前
- 感染症の罹患
その他、アレルゲンに対する耐性(忍容性)を高めるために、減感作療法という治療を行うこともあります。
この治療は、アレルギー症状を起こさない程度の少量のアレルゲンを定期的に摂取することでアレルゲンに対する忍容性を高めていく治療です。
意図的にではありますがアレルゲンに暴露するため、治療に関連してアナフィラキシーを起こしてしまうこともあります。
そのため、この治療を行う場合は専門の医師の指導の下で行ってください。
ただ、このように注意をしていても意図せずアレルゲンに暴露してしまう場合があります。
その際は、迅速なエピペンの使用や早期の治療によりアナフィラキシーショックとなることを抑えることができます。
アナフィラキシーが出現した場合の対応をよく覚えておきましょう。
関連記事:食中毒かもしれない症状を解説!うつる可能性や対処方法は?-横浜内科・在宅クリニック
まとめ
アナフィラキシーショックはアレルゲンへの暴露をきっかけに突然発症します。
それまで健康に生活していた方が死亡してしまったり、大きな後遺症を残してしまったりすることがある病気です。
一方で、発症早期に適切な対応を行い、迅速に医療機関で治療を受けることができれば、後遺症なく退院することが可能な病気でもあります。
子どもで発症することも少なくありません。
患者さん本人だけでなく、その保護者や学校教職員など周囲の人も十分な知識を持っているべき病気です。
長文ではありますが、詳しく解説させていただきました。
ぜひ本記事を参考にしていただき、アナフィラキシーに関する知識を深めていただければ幸いです。
参考文献