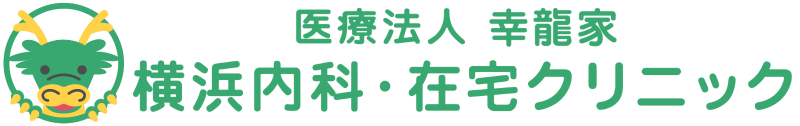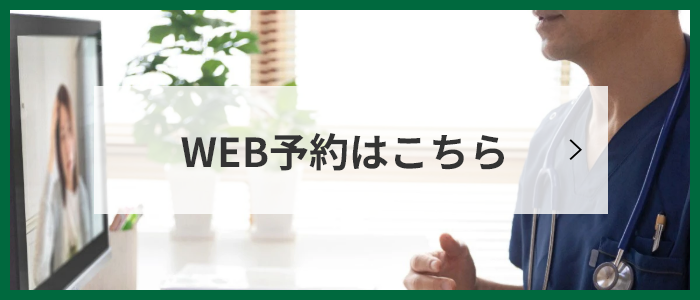子供がお漏らし・おねしょを繰り返す原因|尿失禁・夜尿症とは?
小学生になってもおねしょがなおらない!
お泊りがあるけどおねしょが心配!
今回は、そんな心配がある親御さんへむけて、おねしょと夜尿症について違いや原因を詳しく解説していきます。
夜尿症とおねしょの違い
おねしょとは、4歳以下の子が夜寝ている間に尿をもらしてしまうことです。
幼児は排尿のメカニズムが未熟なため、生理的に寝ている間にも排尿をしてしまいます。
夜尿症とは、「5歳以上で、1か月に1回以上の頻度で、夜間睡眠中に尿をもらしてしまうことが3か月以上つづくもの」と定義されています。
関連記事:【子供の下痢】ロタウィルス感染症の症状や感染経路について解説!予防接種は必要?
夜尿症、昼間尿失禁の原因
お漏らし(夜尿症)の原因
夜尿症の原因は、複数の要因が関与しているとされています。
生まれてから一度も夜尿が消失していた時期がない、もしくは夜尿をしてしまう間隔が6か月より短い場合、下記の3つが組み合わさっている可能性があります。
- 寝ている状態から、尿意によって起きる能力がたりていない
- 夜間の膀胱が尿を貯める能力がたりていない
- 夜間に生成される尿がおおすぎる
また、夜尿が消失していた時期が6か月以上あったのちに夜尿症になってしまった場合は、以下の理由や疾患が原因となって引き起こされている可能性があります。
- 生活上のストレス(保護者の離婚や兄弟ができる等)
- 精神疾患
- 膀胱炎や尿道炎などの下部尿路感染症
- 外傷、てんかん等のけいれん性疾患
- 睡眠時無呼吸症候群
- 糖尿病
- 尿崩症
- 甲状腺機能亢進症
明らかな原因遺伝子は発見されていませんが、両親のいずれかに夜尿症がある場合、そうでない場合と比較して5~7倍夜尿症になりやすくなります。
また、両親とも夜尿症がある場合は11倍夜尿症になりやすいといわれています。
昼間尿失禁の原因
昼間の尿失禁(尿を漏らしてしまうこと)に夜尿症が併発している患者さんは多くいます。
この場合、膀胱や尿道の形態やそれらを支配している神経、機能に何らかの問題がある場合が多いです。
夜尿症は発達障がいと関係があるのか
発達障害である自閉症やADHD(注意欠如・多動症)がある人のうち、10~15%に夜尿症との合併があるとされています。
神経系の発達が未熟な上、夜尿症の治療に必要な夜間の水分制限や排泄習慣を守りにくい、下着が濡れている感覚が鈍いなどのことから夜尿症の治療が難航することもあります。
何歳ごろになると夜尿症が改善するのか
夜尿症の有病率は6歳で13%、10歳で5%、12~14歳で2~3%といわれています。
自然経過だとしても、小学校卒業~中学生くらいで98%程度が夜尿症が改善します。
しかし、夜尿症に対する生活指導をはじめとする治療介入により、自然経過に比べて治癒率を2~3倍高めることができます。
小学生になっても夜尿症が治らない場合は、医療機関に相談し積極的な治療介入をおすすめします。
病院での診察と治療について
夜尿症の相談をしに受診した際にはまず、問診や尿検査等を行い、夜尿症の原因となる疾患が隠れていないかを確認します。
2週間~1か月の生活習慣の改善だけで効果が不十分な場合には、薬物療法やアラーム療法といった装置を用いた治療が行われます。
関連記事:子供がお腹を痛がるときはどうすればいい?考えられる腹痛の原因や危険なサインとは?
自宅でできるお漏らし(夜尿症)とおねしょの対処法
夜尿症には生活習慣の改善が大切です。
生活習慣を改善するだけでも、約2~3割のお子さんのおねしょがなくなるといわれています。
効果のある生活習慣は下記の通りです。
- 早寝、早起きをし、規則正しい生活をする
- 塩分を控える
- 便秘に気を付ける
- 夕食以降の水分摂取はコップ1杯程度に控える
- 寝る前にトイレに行く
- 寝ているときの寒さ(冷え)から守る
- 夜中、無理にトイレに起こさない
夜尿症のお子さんに対する大事な心構えとしては「起こさず、焦らず、怒らず、ほめる、比べない」です。
お子さんやご自身を責めないようにしましょう。
そして、治療に関して約束が守れたり、夜尿がなかった日はしっかりとほめましょう。
横浜内科・在宅クリニックでの対応
横浜内科・在宅クリニックでは、夜尿症についての生活指導をはじめ、薬物療法やアラーム療法を開始できます。
また、難治性の場合では専門医の紹介が可能です。
記事を読んでみて思い当たる症状や、不安がある場合は、気軽にご相談ください。
まとめ
夜尿症はほとんどが自然軽快しますが、治療介入によってより早く治療できます。
なかなか相談しづらいかもしれませんが、お子さんの自己肯定感を守るためお気軽に相談してください。
参考文献
●夜尿症診療ガイドライン2021 日本夜尿症学会 著
●小児科医が知っておきたい 夜尿症のみかた 金子一成 著
●昭和大学藤が丘病院「おしっこトラブルどっとこむ」

ふかしばこどもクリニック 院長 菅谷雅人(小児科専門医)
【経歴】
・東邦大学医学部医学科卒業
・千葉大学医学部付属病院小児科を経て、千葉東病院にて小児腎臓内科診療に従事。
【資格】
・日本小児科学会 小児科専門医
・日本腎臓学会 腎臓専門医
・小児慢性特定疾患指定医

横浜内科・在宅クリニック 理事長:朝岡 龍博 医師
『クリニックに関わる全ての人を幸せに』
『最後まで患者様と病気と向き合います』
【経歴】
・2016年 名古屋市立大学卒業、豊橋市民病院 初期研修医勤務
・2018年 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科
・2020年 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科
・2021年 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科
・2022年 西春内科・在宅クリニック 副院長
・2023年 横浜内科・在宅クリニック 院長
・2025年 医療法人 幸龍家 理事長
【資格】
・舌下免疫療法講習会修了
・厚生労働省 指定オンライン診療研修修了
・緩和ケア研修会修了
・難病指定医
・麻薬施用者